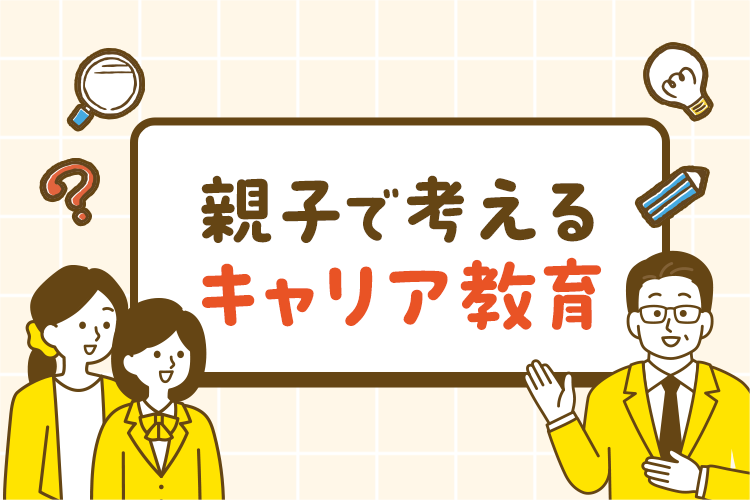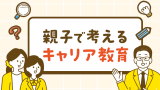キャリア教育の専門家が、読者のみなさんからの相談に答えます。今回は、やりたいことがない、好きなものが見つからない子との関り方について聞きました。

武居秀俊(たけい・ひでとし)
人材系の会社で営業や研修を担当、ヘッドハンティング会社のキャリアコンサルタントを経て、東京の都立高校で世界史教員として勤務。その後独立し、現在は企業向けに経営支援や採用支援を行うほか、中学生~大学生向けにキャリア支援プログラムを提供している。自身は男4人兄弟で、3女の父。
好きなことを見つけるには?
子ども(中1男子)の学習意欲が低く、「勉強が好きでないなら、進学先は普通科高校以外でも……」と考えています。ただ、子ども自身、自分の好きなことが分からない状態で、私もどんなアドバイスすればいいか悩んでいます。子どもが没頭できるくらい好きなことを見つけるには、親としてどのように関わってあげればよいでしょうか?
(49歳、性別無回答)
他にも、「どのような声掛けをすればやる気を引き出せるのか、具体例を教えて欲しい」などの声が届いていました。
武居さんのアドバイスは、次の通りです。
言語化して、強みを意識しよう
子どもに問いかけ、好きなことを言語化してあげよう
「好きなことが見つからない、分からない」という話はとてもよく聞きます。
以前、こちらの記事で、「子どもは周囲の大人から聞かれ、答える過程の“言語化”によって気づきを得る」「問いかけられる体験が人を育てる」ということをお伝えしました。今回はこれをさらに掘り下げてみたいと思います。
人は誰でも、「何かに秀でていたい」「他の人とは異なり自分らしくありたい」という思いを持っています。例えば、サッカーが好きだとしても、自分より上手い人はいくらでもいますよね。そんな時、周りの大人たちが「ドリブルで敵を抜くのが得意」「相手チームのキープレイヤーを見抜くのが上手い」など、その子の強みや好きなことを明確にしてあげるといいですね。

人は、言語化されるとそれを意識するようになります。筋トレでも「上腕二頭筋を鍛える」などと鍛えたい部位を意識した方が効率よくトレーニングできると言われています。言語化した強みが、正解でも不正解でも構いません。意識することで、その子どもが自分らしさを伸ばすことにつながるのです。
強みや好きなことを認識し、自分らしさを発揮できると、子どもはそれに打ち込み、やる気を出します。
「問い」を活用して言語化しよう
子どもの強みや好きなことを、周りの大人はどのように言語化していけばいいのでしょうか。まず「問い」を活用して、子どもに聞いてみてください。その際、名詞ではなく、動詞で答えさせることで、何が好きかをより明確に出来ます。
例:ゲームが好きな子ども(A、B、C)に問いかける場合
Q.ゲームのどんなところが好きなの?
大人:Aは対戦するのが楽しいんだ。友達と一緒に何かをすることが好きなのかな。じゃあ、勉強でもライバルを見つけられるといいかもしれないね。Aが勝ちたかったり、結果を分かち合ったりしたい存在って誰になるの?
大人:Bはレベルアップするのが面白いんだね。頑張ったことで、成長していくのが好きなのかな。じゃあ、勉強でも周りを見るのではなく、過去の自分と比較しての成長を感じられることが大事かもしれないね。今回は、どのくらいの自分の成長を感じられたら満足できそうかな?
大人:Cは分析して動くことが好きなんだ。相手の動きを見ながら考えて、動くことが得意なのかな。じゃあ、勉強でも分析が大事かも知れないね。今回はどういう対策や分析をしていけば、自身が納得する結果になると思う?
子どもの回答に対して、大人が復唱したり、さらに問いを重ねたりすることで、より強みが明確になっていきます。
ここでは、ゲームを例にあげましたが、日常会話の中でもこのような問いを増やしていきましょう。今日学校であった楽しかったこと、休日に一緒に出かけた場所で印象に残ったことなど、どんなことでも構いません。子どもにたくさん問いを投げかけてあげてください。
そして、好きなことだけでなく、苦手なこともきちんと聞いてあげるのが大切です。例えば、単に「数学が苦手」というだけではなく、「数学の文章題を見て、計算式に落とし込むのが苦手」など、不得意な部分が具体的になると、漠然とした苦手意識が軽減し、対策を立てやすくなります。
ただ、問いを活用して好きや強みを言語化しても、子どもが一気にやる気を発揮するわけではありません。このような声掛けは、日々の積み重ねです。
「ウィークタイズ」を活用しよう

社会学では「ウィークタイズ(weak ties/弱い結びつき)」という言葉があります。人は、親などの「強い結びつき」よりも、「弱い結びつき」、つまり、利害関係の少ない人から言われたことの方が、素直に受け入れられたり、自分の判断で動きやすくなったりすることがあります。
そのため、状況によっては親が誘導するよりも、きょうだいや塾・習い事の先生などから声を掛けてもらうことも有効です。「親の言うことを全く聞かない……」という時は、ぜひウィークタイズも活用してみてください。
最後に
たくさんの対話を重ねていく中で、そして人と関わりの中で、子どもは自分の強みや好きなことを認識し、自分らしい道を選べるようになります。ぜひ、そんな後押しをするようなコミュニケーションを心がけていってくださいね。