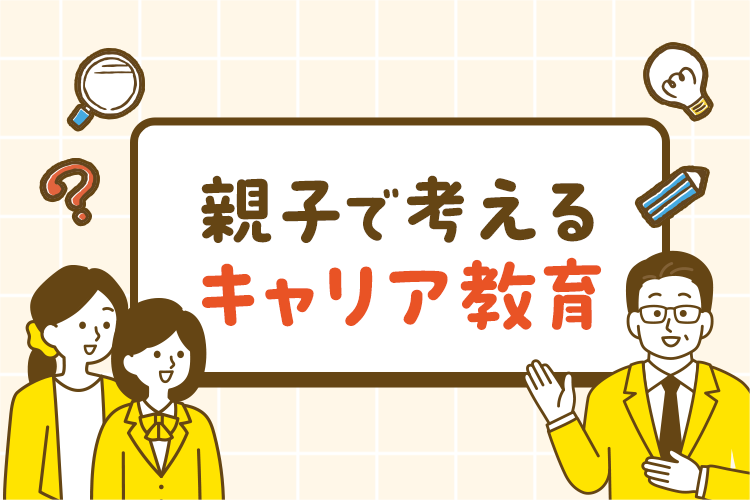キャリア教育の専門家が、読者のみなさんからの相談に答えます。今回は、子どもに元気がない時の関わり方について聞きました。

武居秀俊(たけい・ひでとし)
人材系の会社で営業や研修を担当、ヘッドハンティング会社のキャリアコンサルタントを経て、東京の都立高校で世界史教員として勤務。その後独立し、現在は企業向けに経営支援や採用支援を行うほか、中学生~大学生向けにキャリア支援プログラムを提供している。自身は男4人兄弟で、3女の父。
子どもの変化に気づくために
学童で働いています。夏休み明けは、落ち着きのない子や元気のない子が増えるように感じています。私が「どうしたの?」と聞き、理由を話してくれる子はいいのですが、「別に」と言って何も答えてくれない子もいます。そんな子たちに、どのように関わればよいでしょうか?
(29歳、女性)

9月は、不登校の子どもが増えたり、夏の疲れが表面化したりしやすい時期だといわれています。学校側にとっても秋は運動会・体育祭や文化祭、音楽コンクールなどの行事が重なるシーズン。新しいことが重なると、大人だけでなく、子どもも疲れてしまいます。
特に近年は猛暑が続いており、そんな気候の厳しさもストレスを増幅させる要因です。だからこそ、私たち大人が子どもの小さな変化に気づき、敏感になる必要があります。私自身、教員として勤務している頃は、挨拶や授業中の反応、休み時間の過ごし方、会話量など、生徒たちの変化を観察するようにしていました。
相談者さんも、子どもたちの普段の様子を観察して、「今日はちょっと違うな」と気づいたら、まずは声をかけ、疲れている時は労って、寄り添ってあげてください。本人が何も答えたがらないようなら、無理に聞き出さなくても構いません。まずは「気にかける」ということが大切です。その点では、すでに相談者さんは適切に対応できていると思います。
教育のゴールは「自律」

教育のゴールは、「セルフマネジメント」が出来るようになることです。具体的には、次の3つが重要だと考えています。
- 疲れている時に、きちんと休めること
- 自分の出来ること・得意なことを認識し、それを活かしていくこと
- 苦手な部分は人に頼って、助けてもらうこと
心と体の変化に気づき、コントロールする
「ストレス」という単語は、もともと物理学で使われていたそうです。金属疲労とは、小さな力であっても、繰返し負荷を受け続けることで、小さな割れが発生し、最終的には破壊にいたる現象です。これは、人間にも言えることではないでしょうか。
大人であれば、疲れていたら、「今日は休もう」と判断できますが、子どもの場合、そうした力が未発達です。だからこそ、身近な大人が「休んでもいいんだよ」と伝えたり、リラックスできるきっかけをつくってあげたりすることが有効です。
自分自身の心と体の変化に気づき、適切に休んだり、スピードを緩めたり、コントロールできる力を身に付けるのは、生きていくために必要な力と言えるでしょう。
「Give」が出来る人になること

子どもは、「自分が得意だと思えること」を見つけられると、自信とエネルギーが湧いてきます。勉強だけでなく、スポーツや趣味、何でもいいです。さまざまな体験を重ねる中で「自分はこれが得意なんだ」と気づくことが出来るといいですね。
苦手なことがあっても、すべて克服する必要はなく、多少は抱えたままでも構いません。大事なのは、苦手なことや出来ないことがあった時、周りの人に「助けて」と言える関係性を築くこと。その分、自分が得意なことで、相手にお返しすればいいのです。
そうしたGive&Takeの関係の中で、人は成長していきます。誰かに対して「Give」が出来る強みを見つけて、ぜひ伸ばしていってください。それが「自律」に繋がるのではないでしょうか。
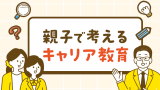
「気にかけてくれる人」の存在
私自身、小学校5年生の頃に不登校を経験しました。当時は将棋に熱中し、地域の大会で「小学生名人」になるほどの実力はあったものの、学校に行く意味も、勉強する意味も見出せていませんでした。当然、学校の成績も良くなかったです。
中学生になった時、別の学校に進学した将棋仲間の母親が亡くなりました。彼のことが気になって、家を訪ね、他愛もない話をしていましたが、その時、「うちのおふくろが、武居のことすごくいいって言っていたよ」と口にしました。その言葉を聞いて、号泣。帰り道、夜空の満月がきれいだったことを今でもはっきり覚えています。

彼の母親とすごく仲が良かったわけではありません。ただ、「自分のことを見てくれて、認めてくれる大人がいる」と思えたことがすごくうれしくて、自信になりました。その日を境に「世の中を信じていい」という感覚になり、学校へ行くことや勉強に対しても前向きに取り組めるようになりました。
みんなで子どもを育てる社会へ
子育ては決して父親・母親だけで行うものではありません。祖父母や学校、塾、学童、地域の人など、多様な大人が関わることで、子どもは心理的に安定し、自分らしく成長できます。
「子どもを育てる」という営みを、家庭や学校だけに押しつけるのではなく、社会全体で担っていく。その余裕のある社会こそが、子どもたちを守り、未来を豊かにしていくのだと思います。
ぜひ、子どもの小さな変化を見逃さず、得意分野を伸ばす機会を与えてあげてください。それは、自分の子どもだけはなく、関わる子ども全てに対してです。ぜひ、みんなで子育てをしていきましょう。
……………
「親子で考えるキャリア教育」の連載は今回で終了になります。これまでお読みいただき、ありがとうございました。