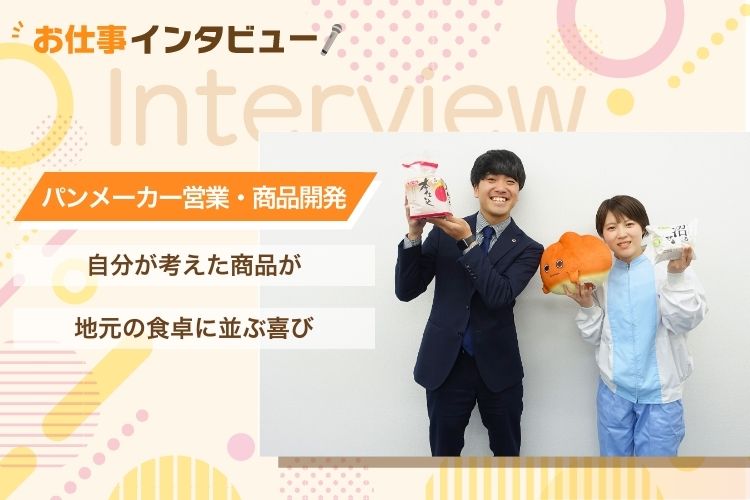きずなネットでは、進路や職業選びの参考にしてもらえるよう、さまざまな仕事に携わる人の声を紹介しています。
今回は、事前アンケートでも人気のあった職業「研究者」です。研究者の活躍の場は、大学や研究所、民間企業などさまざま。何をテーマに、どこで研究するかによって働き方は変わります。そして、自分が探究するテーマに対して、大学から大学院へ進んだのちに、その職業に就く方が大半になります。今回は、医薬品の研究開発を手掛ける創薬企業で働く研究者の方にお話を聞きました。

39歳/7年目
研究者(医薬品研究開発)
子どもの頃の夢は?
医療関係の仕事に就きたいと思っていました。父が放射線技師、母が保健師で、医療に携わる仕事が身近だったためです。
この仕事についたきっかけは?
あえて創薬研究を選んだわけではなく、これまでの研究者としてのキャリアが活かせる仕事をしたいと思い、選んだ道です。
小さい頃から医療関係の仕事に興味があったので、薬をつくる仕事は意図せず夢が叶ったのかもしれません。また、自分の性格を考えて、大企業よりもベンチャー企業の方が向いていると感じていたこともあり、今の会社を選びました。
大学では、植物生理学の研究(※1)をしていて、大学院で博士号を取得した後は3年ほど、大学で研究員として働いていました。その間に、海外の研究室に留学もしました。
大学での研究は「大発見」が目標で、それはそれでとてもやりがいがあり、一生懸命になれる仕事でした。ただ、もっと直接的に人のためになる実感が得られる仕事がしたいと感じ、「モノをつくりだす企業」の研究員になることを選択しました。
………………
※1:植物の生理現象を分子レベルで理解するための研究。主に取り組んでいたのは、植物の高温応答について。感覚器官のない植物はどのようにして外界の環境の変化を感知するのか。細胞の内外で水の通り道をつくるアクアポリンというタンパク質に注目して遺伝子発現解析やタンパク質の発現解析などを行っていました。
仕事内容は?

医薬品の研究開発を手掛ける創薬企業で研究をしています。まだ世の中にない新しい薬をゼロから創り出す仕事です。
ある1日の流れ
9時
メールチェック、バイオ・医療関連のニュースをチェック
10時
会議・打合せ、今日の実験計画の確認
12時
お昼休み、新着論文のチェック
13時
実験
17時
データ解析と実験ノートの記入
18時30分
メールチェック、翌日の実験計画の作成
19時
業務終了
ここでは、実験をしていた頃の1日の仕事の流れを書きました(※2)。研究はチームで行っています。大学での研究よりも、会社に入ってからの研究の方が、役割が細分化されているので、よりチーム力が重要となります。
また、取引先は製薬企業やバイオベンチャー企業などで、他の会社と共同研究をすることもあります。私の会社は製造や販売は行っておらず、臨床試験(人での開発、いわゆる治験)も最終段階までは行いません。薬の「種」をゼロから創り出し育て、開発を行う会社に導出するビジネスモデルです。
たとえば、ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンは、元々はビオンテックという会社がつくったもの。このように、薬は大手の製薬企業だけで作られているのではなく、世界中の多くのベンチャー企業がつくりだしたものを大手企業が開発や申請を行い、人に使われる薬になっていきます。
………………
※2:昨年から管理職になったため、今の仕事はマネージメント業務や社外とのやり取りがメインに。これまでは自分の携わるプロジェクトについてだけ理解・把握していればよかったのですが、今は自分のグループの研究員が携わるプロジェクト全ての内容や進捗も把握する必要があります。必然的に勉強することは増えました。ただ、マネージメント業務は苦手ではないようなので、あまり苦には感じていません。まだプロジェクトのリーダー業務もおこなっているので、優先順位を考えながら進めています。
研究者のイメージと、実際の仕事とのギャップは?
イメージ通りでした。大学の研究者は、論文を書いて研究費を獲得する仕事。企業の研究者は、製品につながるような成果を出す仕事です。分野や業界に関わらず、研究者は自身の専門に関わる勉強を日々していると思います。
仕事につくために努力したこと
大学では全く異なる分野の研究をしていたので、会社に入ってから教科書を買ってイチから薬の勉強を始めました。
また、論文の多くは英語で、分野によって使われる専門用語が全く異なります。大学での研究から分野が変わったことで、入社当初は1本の論文を読むのにも一苦労だったことは衝撃でした。
創薬の研究は世界中で競争が激しい分野です。そのため、いち早く新しい情報を入手して新しい研究に取り掛かることが重要。日々、最新の論文やニュースをチェックして乗り遅れないように努力しています。
仕事の楽しいところ・やりがい
研究は仮説と検証の繰り返しです。自分の考えた仮説が検証実験により実証された時は大きな達成感が得られます。
また、創薬においては、人での臨床試験に進むまでに、大小いくつもの関門があります。自分達のつくりだした「薬の種」がその関門をひとつずつ突破できる喜びの積み重ねが、創薬研究者のやりがいに繋がっていると思います。
仕事の大変なところ
創薬は非常に長い道のり。新薬が患者さんの元に届けられるまでには数々の研究や試験に加え、厳しい審査を経る必要があります。
研究段階から承認までは10年以上もかかります。また、創薬の成功確率は2万分の1や3万分の1といわれています。創薬研究者の多くは、研究者人生で携わったプロジェクトから1つも薬にならない(製品化されない)ことも珍しくありません。
仕事とプライベートは、どう切り替えている?
好きなことなので、休日やプライベートの時間に仕事に関わる調べものや勉強をすることも、趣味の一環のような感じかもしれません。
たとえば、ランニングや山が趣味なので、ランナーや登山などのツイッターをフォローしています。同じように製薬企業や研究者のツイッターもフォローしています。仕事だからという訳ではなく、興味のあることだから情報を入手したいという思いです。
将来の目標や夢は?
自分の携わった研究から新薬が生まれ、患者さんの元に届けられることが今の夢です。
将来この仕事につきたい人へ
研究は日本にとどまらないグローバルな仕事。どのような分野の研究でも英語力は重要だと思います。また、研究者は1人で黙々と打ち込んでいるイメージですが、研究は1人では成功しません。さまざまな人と協力して一緒に研究する力も必要です。
この記事の感想や「こんな人の話を聞きたい!」「こんな仕事に興味がある!」自薦・他薦問わず「この人にインタビューしてほしい!」など。みなさんの声をお待ちしています。
★投稿はこちらからどうぞ★