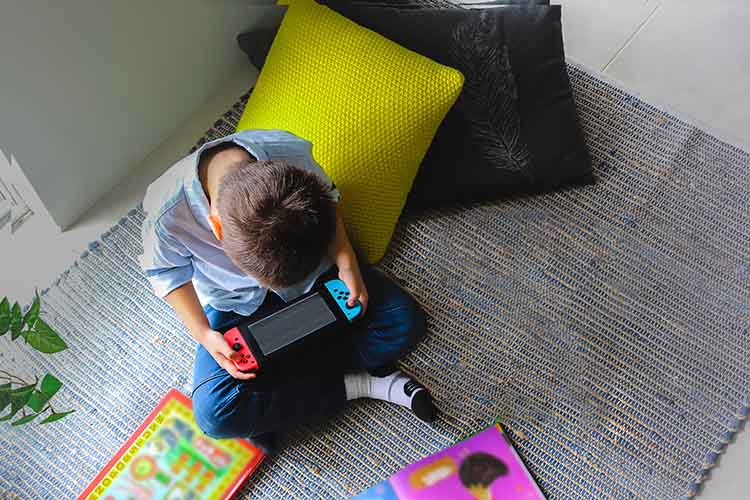子どもの不登校は年々増加しており、学校や教育委員会、関連機関、支援団体などでさまざまな対策がとられています。不登校は「学校を継続的に休むこと」というイメージでいる方も多いかもしれませんが、文部科学省の設定した明確な定義があります。今回は、不登校の定義や現状、受けられる支援や不登校の課題について解説します。
不登校とは?その定義は?

不登校と聞くと、長い間学校に通えていない子のイメージを持っていませんか?しかし、不登校の定義は1年のうち多くを休むというものではありません。文部科学省では、不登校を下記の通り定義しています。
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの。
引用:不登校の現状に関する認識/文部科学省(※1)
文部科学省の定義では、病気や経済的な理由以外により年間30日以上学校を休むと不登校に当たるというわけです。
継続して休まずとも、年間30日以上学校を欠席すると不登校に該当します。つまり、文部科学省から発表される不登校の児童・生徒数は、この定義にあてはまる児童・生徒の数を集計したもの。
不登校の現状や現行の支援、不登校の課題について、次章から詳しく解説します。
不登校の現状

テレビやネットニュースなどのメディアでは、不登校の児童・生徒数増加がたびたび取り上げられています。
子を持つ親御さんは、自分の子どもの状況と重ね、気になってしまうのではないでしょうか。
しかし、不登校は増加しているとはいえ、それほど多いわけではありません。
令和2年度の調査によると、不登校の児童・生徒の割合は、
- 小学生 1%
- 中学生 約4%
- 高校生 約1.4%
です。(※2)
数字を見ると、中学生の不登校が多いのは明らかです。中学生の不登校の割合は、8年前の約2倍となっており8年連続で増加しています。
また小学生も、同様で中学生よりも不登校の割合は少ないものの、8年前の約2倍と増加傾向にあります。
ただ小中学生の不登校は8年連続で増加している一方、高校生の不登校は平成30年~令和2年にかけては減少傾向にあります。
中学生は、不登校の割合が高いだけでなく、不登校が長期間続いている割合も高いようです。
不登校の学校を休んだ日数を見ると、90日以上の長期にわたり学校に行っていない児童・生徒も少なくありません。
90日以上の不登校の割合は、不登校全体の
- 小学生 43.8%
- 中学生 60.3%
- 高校生 19.6%
です。(※2)
中学生は、不登校の生徒のうち約6割は長期的に学校に通えていないことが分かります。ただ90日以上学校を休んでいても、1日も出席していない生徒の割合は5%未満と少数。
多くは出席日数が11日以上であり、学校等に行く日もあることが分かります。
出席日数については、次章で詳しく解説します。
不登校の支援・対策は?

不登校が増加するにあたり、文部科学省もさまざまな対策をとっています。具体的には、学校をはじめとする相談窓口の設置や、学校以外の教育機関の設置、民間の教育機関との連携などです。
不登校の支援機関
不登校になった場合に相談できる窓口は、いくつか用意されています。学校のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが配置されている学校であれば、これらは一番身近な窓口です。
ただ、不登校の原因が学校にある場合、学校に直接相談しづらい場合もあるかもしれません。
学校以外にも、教育委員会の相談窓口や教育支援センター、児童相談所、民間のフリースクールなどが不登校を支援しています。
不登校支援の基本姿勢
文部科学省は、不登校に対する基本姿勢として「学校に復学すること」が目標ではなく、社会的自立を目指すのが基本的な支援の考え方だと示しています。(※3)
ひと昔前の2016年以前の不登校の支援は、学校への復学に重点が置かれていました。しかし、2016年の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」を機に、無理して学校に再登校する必要はないとの認識に変わりました。(※4)
現在では文部科学省も、学校への復学を目指すだけでなく、夜間中学など学校とは別の教育機関も含めた学びの機会を得ることが重要だとしています。
ひと昔前とは、不登校の支援に対する考え方も変わっており、条件を満たせば、学校以外の機関での学びの時間も出席日数として認められます。
学校以外も出席扱いになる
不登校になり教育支援センターや夜間中学、フリースクール等に通う場合、一定の要件を満たし、在校している学校の校長に認められれば出席扱いとなります。
一定の要件とは、
- 保護者と学校の連携が十分で協力できていること
- 基本的には教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関が対象
- 公的機関に通えない場合は民間の相談・指導施設も考慮される
(ただし校長が生徒にとって適切な指導と判断した場合に限る) - 学校外の機関へ通所や入所して相談や指導を受けることを前提とする
- 学校外の学習評価を学校が適切に行い生徒や保護者、学校外機関に伝えること
の5点です。(※5)
出席扱いとみなされるのは、この5点を満たし校長が認める場合です。
基本的には教育支援センターなどの公的機関が対象ですが、指導内容が適切であればフリースクールやオンラインスクールも認められる可能性があります。
詳しくは、文部科学省の「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(※6)の資料で開示されています。
ひきこもりとの違いは?

不登校というと、学校に行けず家にひきこもっているイメージを持つ方もいるかもしれませんね。ただ不登校はひきもこりとは異なります。
厚生労働省の定義するひきこもりは、6ヶ月以上社会的な関わりがなく、家などにとどまっている状態を指します。(※7)
不登校は、学校を年間30日以上休むこと。不登校の子は、学校を休んでもフリースクールや習い事、塾などには通えるケースもあり、不登校=ひきこもりとは言えません。
ただしある調査では、不登校の経験があると、不登校経験がないよりも、ひきこもりやニートを経験する割合が高いことが報告されています。(※8)
不登校でひきこもりを経験する子の割合は約半数。不登校からひきこもりにならないよう、適切な支援が求められています。
最後に

不登校の児童・生徒数は増加しており、親としては他人事と済ませられない場合も珍しくないかもしれません。最近では、学校に通えない場合でも、無理に学校に通わせる必要はないとの認識が広がっています。
学校以外でも、市区町村の教育支援センターやフリースクール、オンラインスクールなどで学べる機関が増えています。子どもに合った適切な場所を見つけてあげる選択肢も視野に入れておけるとよいでしょう。
もし子どもが不登校ぎみだったり、不登校になってしまったりした場合は、一人で抱えこまずに、早めに適切な機関へ相談することをおすすめします。
文:COE LOG編集部
あわせて読みたい
- 不登校の原因とは?親のNG対応と心構えを解説
- 小学生の不登校の現状は?スクールカウンセラーインタビュー
- 中学生の不登校|「聞く」にフォーカスした、親の対応事例
- 小学生・中学生の不登校支援|電話相談窓口インタビュー
- 朝起きられない子供「起立性調節障害」とは?【医師解説】
- 「学校に行きたくない」と言われたら?不登校の原因と考え方【医師解説】
※1 不登校の現状に関する認識/文部科学省
※2 令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要/文部科学省
※3 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針(概要)/文部科学省
※4 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)/文部科学省
※5 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて/文部科学省
※6 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて/文部科学省
※7 「ひきこもり」の定義など/厚生労働省
※8 子供・若者の意識に関する調査(令和元年度)/内閣府