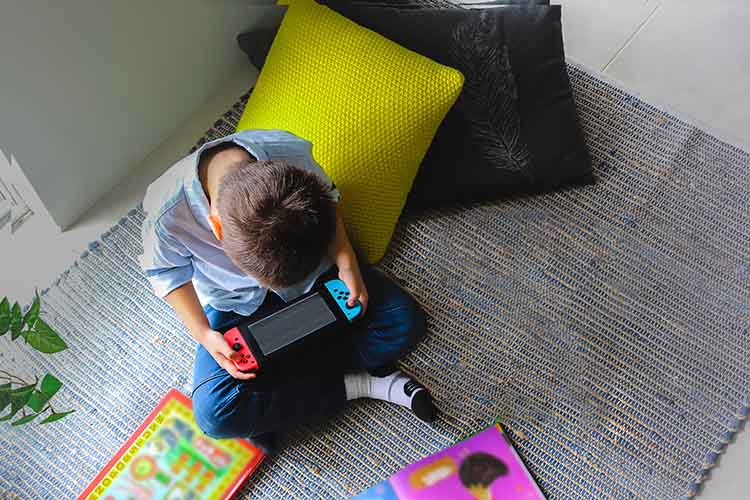HSCとは、Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)の略で、生まれつき敏感で繊細な子どものこと。他の人から見たら「そんなの気にしなくていいのに…」ということを敏感に感じ取ってしまいます。園や学校など、集団生活の中でどうしても疲れやすくなってしまうHSC。今回は、HSCの子どもを持つママ向けに交流会を開催している、ママのためのメンタルコーチ 高波ヤスコさんに、HSCの特徴や対処法を聞きました。

ママのためのメンタルコーチ:高波ヤスコさん
まずは子どもの特性を知ること。そのままのわが子を受け入れ、合わせた対策をしていくことが大切です。
HSCとはどんな子ども?特徴は?

HSCとは、生まれつき敏感で繊細な子どものことを指します。
繊細さん・敏感さんともいわれる大人は、HSP(Highly Sensitive Person/ハイリ―・センシティブ・パーソン)。子どもの場合は、HSC(Highly Sensitive Child/ハイリー・センシティブ・チャイルド)といわれます。
これは、生まれつき持つ性格的な特性で、アメリカの心理学者エイレン・アーロン博士によって名付けられました。全人口の5人に1人が該当し、人よりも刺激に敏感で、疲れやすくなってしまう大人や子どものこと。
アーロン博士は、HSCには「DOES(ダズ)」という4つの特徴があると言っています。
- D(物事の考え方が深い:Depth of processing)
- O(刺激に敏感である:Overstimulated)
- E(共感しやすい:Emotional reactivity and high Empathy)
- S(感覚が鋭い:Sensitivity to Subtleties)
物事の考え方が深い:Depth of processing
人に対する感受性が高く、物事を深く考えるため、行動するまでに時間がかかります。1を聞いて、10を想像して考えられる思考力を持ち、調べ物をする際も深く掘り下げることができます。
刺激に敏感である:Overstimulated
人の大勢集まる場所が苦手で、大きな音に過剰なほど驚いてしまいます。友達と過ごす時間が楽しいものの、気疲れしやすく、家に帰る頃にはどっと疲れが出てしまうことも。人に言われた些細な一言を、いつまでも気にしてしまうこともあります。
共感しやすい:Emotional reactivity and high Empathy
人の気持ちに流されやすく、共感能力が高いのも特徴。絵本やニュースなども感情移入しすぎて、自分のことのように喜んだり悲しんだりします。また、人が怒られていると自分も怒られているように感じ、気分が落ち込んだり、傷ついたりすることも。仕草、目線、声色などにも敏感で、相手の機嫌や気分、気持ちの変化にすぐ気づくことができます。
感覚が鋭い:Sensitivity to Subtleties
冷蔵庫などの電化製品の音や時計の秒針の音など、些細な生活音が気になってしまいます。
人の体臭や口臭、タバコ臭などに対してすぐに気分が悪くなる、肌着のタグやチクチクする素材が気になる、など。あらゆる感覚が鋭いため、気が散りやすく、集中できなくなることがあります。
HSCとは、上記の4つすべてに当てはまることが条件。そして、同じHSC、繊細で敏感な子どもでも、どのような刺激に影響を受けやすいかは違っています。
たとえば、私のように音に敏感だというケースもあれば、皮膚の感覚が敏感というケースも。
特に、学校のような集団生活が行われる場では、刺激に敏感な子どもは疲れやすくなってしまいます。
HSCの子どもの特徴としては、「他の子と自分との境界線があいまいなこと」が挙げられます。クラスの子が怒られていると自分が怒られているような気持ちになる、誰かが辛い思いをしているとすぐに気づくなど。他にも、ヒソヒソ話が全部聞こえてしまう、大きな声を出す子が苦手なども。クラス替え等の環境の変化やイベントごともストレスになってしまいがちです。
また、こういったことが引き金で、疲れを溜めやすくなり、自分に自信がなくなってしまうことも。
HSCの子どもを持つママの声

私自身がHSPで、長女もHSCです。以前は、みんなが私と同じようにイライラを感じたり、疲れたりしているのだと思っていました。
きっかけは、ママ向けのイライラ対策講座を受講した際のこと。参加したママたちが、どんな時にイライラするかをシェアする時間がありました。
私は、「お皿のカチャカチャする音が気になる」「子どものキンキン声に疲れる」など、とにかく音に対してのイライラが多かったのに対し、他の人は全く気にしていない様子。自分の感覚と他の人の感覚が違うことに驚きました。
繊細さん・敏感さんという言葉は知っていましたが、まさか自分のことだとは思っておらず…。その経験がきっかけとなり、以前から知識として知っていたHSPに自分が当てはまると気づいたのです。自分がHSPだと知り、その特性を理解することで、適切な対処法をとることができるようになりました。
まずは、自分自身を知ること、子どものことを知ること。それによって、必要以上に疲れない付き合い方・対処法をとることができるようになります。私と同じように悩んでいる方に伝えていきたいと思い、交流会を開催するようになりました。
HSCの子どもの接し方
 HSP・HSCのママ向け交流会、開催時の写真
HSP・HSCのママ向け交流会、開催時の写真
HSCの子どもを持つママ・パパ向けに交流会を開催する中で、参加された方の関心事は、子どもとどう接するか。
HSCの子どもを持つママ・パパの中には、自分自身がHSPである場合と、そうでない場合があります。
自分自身がHSPであれば、こうした子どもの行動や気持ちも比較的理解しやすい傾向があります。非HSPの場合は、子どもの気持ちが理解できず「そんなの気にしすぎ」「気にしなくていいよ」と言ってしまいがち。
すぐに泣いてしまう、なかなか泣き止まない、かんしゃくを起こす、ちょっとしたことを怖がる、人見知りが激しいなど。人と同じようにできないこと、刺激に対して反応している気持ちを否定してしまうと、子どもが自信をなくしてしまうことになりかねません。
大切なのは、気持ちに寄り添ってあげること。子どもを受け入れてあげて、必要に応じた対策をとることです。
どうすればいい?具体的な対処法
HSCのママ・パパが実践していることや私自身が実践して効果があった対処法を、以下にご紹介します。
子どもの話を聞いてあげる
何よりこれが一番大切になります。何に対して反応しているのか、どう感じているのか、しっかり子どもに向き合い、受け入れ、共感してあげること。HSCは病気ではなく、性格的な特性です。話を聞いてあげて、子どもの気持ちを尊重してあげましょう。
刺激の少ない環境をつくる

小さな刺激に対しても反応してしまうHSCは、「気にしない」ことが難しいです。そのため、可能な範囲で、刺激の少ない環境をつくっていけることが望ましいです。
私の娘の場合は、特に音に敏感です。クラスに大きな声の子がいたため、担任の先生に事情を伝え、席を離していただきました。
また、夫と言い合いをしている姿を見せると必要以上に心配をしてしまうため、娘の前では言い合いをしないようにしています。
私自身も音に敏感なため「イヤーマフ」といわれる防音保護具を使っています。娘にも同じものを買い与えました。
具体的に相手にして欲しいことを伝える
学校の先生に「娘はHSCなので…」と伝えても、相手はどうしたら良いか分からず困ってしまいます。
「○○が苦手なので・・・して欲しい」など、具体的にお願いしたいことを伝えます。
これは、家族に対しても同じ。私自身もHSPなので、家族に対してもできるだけ具体的に「こうして欲しい」を伝えています。
健康管理を大切に
睡眠不足はイライラにつながりやすくなるため、睡眠時間をしっかり確保すること。また、適度な運動がストレス発散になるため、体を動かすことも心がけます。リラックスタイムもつくり、基本的な生活習慣を整えてあげることも大切です。
大人の場合、HSPの方には、瞑想もおすすめですよ。
最後に

HSCとは、障害でも病気でもなく、生まれ持った子どもの個性です。他の人よりも物事を深く考えられることや、細かなことに気づけることは、長所にもなります。
そして、私は、子どもがHSCであるか・ないかを知ることはそんなに大切ではないと思っています。
それよりも、どんな特性を持っていようとも、子どもの個性を認めること。その個性に合わせて接してあげることが必要だと考えています。
ママやパパがありのままの子どもを認めて、受け入れてあげること。それが一番、子どもが健やかに成長する土台になっていくのではないでしょうか。

新潟県在住、一男二女のママ。子育てが辛く、心身ともに限界を感じたことをきっかけにコーチングとカウンセリングを学び、体調が改善。メンタルコーチングやママ向けの講座、交流会などを通じ、幸せなママを増やす活動をしています。
https://ameblo.jp/yasuko-kokoro/
あわせて読みたい
- 生きづらさを感じてる?それってHSPかも…特徴と対処法
- 【HSS型HSPとは】矛盾に苦しむ・・・社交的で刺激を求めるのに傷つきやすい人
- 人と関わりたくない、人と会うと疲れるのはHSP?7つの対処法
- HSP・繊細さんの5つの長所!強みを活かす3つのポイント
- HSPの人に言ってはいけない言葉に注意!HSPの彼女/彼との付き合い方は?
文・聞き手:三輪田理恵