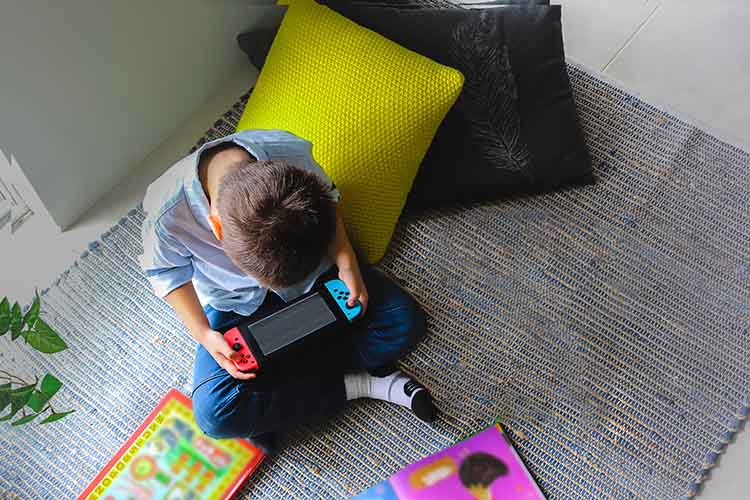中学生の不登校の割合は約4%(2021年文部科学省調査)、特にここ数年は増加傾向であり、決して珍しいことではありません。
不登校になる理由はさまざまで、対応についても正解があるとは言えないのが現状です。今回は、お子さんが不登校になった経験をもつ子育てコーチング協会の谷川さんにインタビュー。その中で大切にしてきた「聞く」にフォーカスした対応を教えていただきました。

お話を聞いた人:谷川明子さん
一般社団法人子育てコーチング協会認定マスターインストラクター。不登校や子育てに悩む親御さんに向けて、子どもの話を「聞く」に特化した子育てコーチング講座を日本全国、韓国でも多数開催。心配ばかりだった子育てが、安心して応援できる親子関係に変わる!との定評がある。
中学生の娘が不登校に

20歳の一人娘がいますが、中学生の時に不登校になりました。
私自身も不登校の経験があり、心の中では「学校に行かなくても大丈夫」と思っていたはず。でも、親の立場で経験すると不安で押しつぶされそうでした。
小学校までは、「プールがイヤ」など、嫌いな授業のある日に渋ることはありましたが、励ませば普通に学校に通っていました。
中学校は、本人の希望で県外の私立中学校に入学。
しかし、中学1年生の夏休み明け頃から「学校に行くのが苦しい」と言うようになり、学校からも「授業に来ていない」と連絡が入るようになりました。
そして、中学1年生の秋頃から不登校の状態に。ここから1年は、原因探しと説得に入りますが、本人は「分からない」と答えるばかり。
さまざまなやりとりを重ね、地元の公立中学校に転籍することになりました。
転籍手続きをする際に、「話し合いたい」と言っても、娘は「分からない」「消えてしまいたい」を繰り返します。そして、絞り出すように言った言葉は、
「お母さんは、一度も私の話を聞いてくれたことがない。だから、話したくない。」
この言葉に、心を打ち砕かれるようなショックを受けました。
>>HSCとは?特徴と対策は?敏感で繊細な子どもは5人に1人!
「聞く」って何?からのスタート

今まで、こんなに娘の話を聞いてきたはずなのに。「聞く」って一体何だろう・・・と、インターネットで「聞く」について検索し、コーチング(※)に出会いました。
コーチング講座に通い、自分が話を聞いてもらうことで初めて「聞く」の意味が分かった気がします。今まで、私自身が人に話をきちんと聞いてもらった経験もなかったように思います。
その上で、「聞く」スキルを学び、不登校の娘に対しては主に以下の2つをおこないました。
受けとめる
相手の話をジャッジしないで「受けとめる」ということをおこないました。
今までは、娘の話に対して自分の意見や想いを伝えていました。
例えば、「学校に行きたくない」という言葉に対して「行かなくてもいいよ」とか「みんなも頑張っているんだよ」など。
特に「消えてしまいたい」など、親として聞きづらいことを言われると「そんなこと言わないで」と口にしてしまうことも。
「受けとめる」というのは、言われた言葉に対して、自分自身のジャッジを入れずに「そう思うんだね」「そんなに辛いんだね」と共感をします。否定も肯定もしないで、そのまま相手の気持ちを「受けとめる」ことを心掛けました。
最後まで聞く
今までは、娘の話の途中で口を挟んでしまうことがよくありました。前述の「受けとめる」で共感しながら、最後まで話を聞くようにしました。
まずは雑談から「受けとめる」「最後まで聞く」を実践したところ、娘の話す量が増えてきました。
話す量が増えてくると、親として聞きたくないことも増えてきます。
ただ、そう思っても「最後まで聞く」ことを心掛けました。
「聞く」を学び、実践する前、私は14年間娘と話して「楽しい」と思ったことが一度もありませんでした。しかし、「受けとめる」「最後まで聞く」を心掛けるようになったら、娘との会話を楽しめるように。
中学2年生の秋頃までは、娘の命を守ることと、自分を信頼して貰うことを最優先にしてきました。話を聞くようになってからは、少しずつ元気を取り戻してきたように思います。
中学3年生になり進路を決めるあたりから、たくさんの話ができるように。娘の希望を聞き、通信制高校への進学を決めました。
不登校の原因探しをやめる

娘は、地元の公立中学校に転籍した後も、卒業まで学校に通うことができませんでした。しかし、自分の意志で高校進学を決め、その後専門学校へ進み、好きな道を歩んでいます。
不登校になった頃は、原因を探し、それを潰そうと必死でした。でも、結局のところ原因を話してくれたのは何年も経ってから。そして、その原因も取り除いてあげられるものでもありませんでした。
原因探しに躍起になるのではなく、まずは気持ちを受けとめてあげること。話してもらえる信頼関係をつくること。進路を決める際は、娘の気持ちを尊重し、どのようにすればやりたいことを実現できるかを一緒になって考えました。
高校進学、専門学校、現在に至るまで、もちろん良いときばかりではありません。ただ、20歳になった娘とはきちんとお互いの思いを話せるようになり、彼女は自分の意志で自分の道を選択しています。
私たちは決して、よく出来た親子ではありません。ぶつからない親子ではなく、ぶつかっても大丈夫と思える、お互いを信じあえる親子になりました。
自分の心の声を「聞く」「聴く」
相手の話を「聞く」ことも大切ですが、同じくらい、それ以上に自分の心の声を「聴く」ということも大切にしています。
私は娘に対して、学校に行ってくれたらいいなという気持ちも持っていました。そんな自分の心の声も、「聴く」を学び自分で受けとめられたことで、娘のことも「受けとめる」ベースができたように思います。
自分の気持ちに蓋をしないこと。信頼できる相手に聞いてもらうことも有効ですので、ぜひ試してみてください。
最後に
私は不器用なので、「聞く」ことしかできません。しかし、「聞く」ことが相手との信頼関係・そのままの自分を受け入れる(自己受容)ベースになると思っています。
不登校である・なしに関わらず、そして親子関係だけでなく全ての人間関係において「聞く」スキルは役に立ちます。
最初の頃は、娘に「その聞き方、気持ち悪い」と言われたこともありました。それでも粘り強く続けることが、信頼関係をつくることにつながりました。
まずは、「受けとめる」「最後まで聞く」を試してみてください。続けることで、会話が変わってくると思いますよ。
情報提供:一般社団法人子育てコーチング協会
文・聞き手:COE LOG編集部
※コーチング:語源は英語のCOACH(馬車)で、「人を目的地まで送り届ける」という意味から、相手の目標達成に向けて支援すること。相手の話を聞き、承認し、質問するなどで、自発的な行動を促すコミュニケーションの技法といわれています。
あわせて読みたい