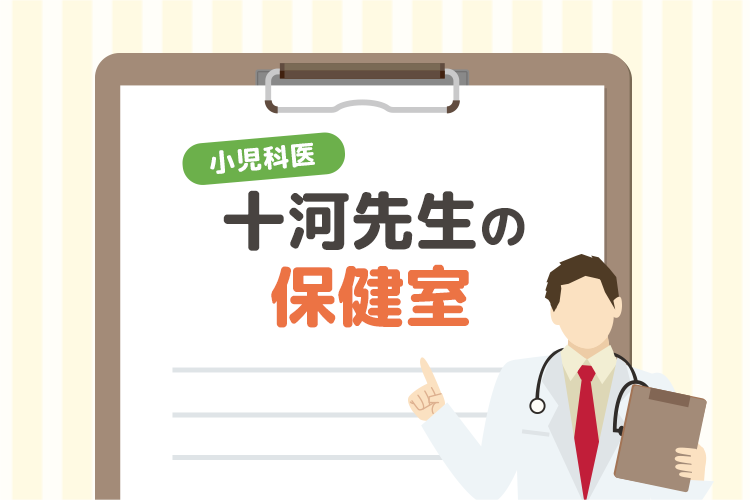- 投稿日
睡眠時の大きないびきを人から指摘されて、放置していませんか? ほかにも起きた時の口の渇きなど、「花粉症で鼻が詰まっているから」と自己判断でそのままにしている人もいるかもしれません。しかしその症状、実は「睡眠時無呼吸症候群」が原因かもしれません。
睡眠時無呼吸症候群には、重大な病気が潜んでいることもあります。ここでは、睡眠時無呼吸症候群の症状と治療法について、耳鼻咽喉科専門医に解説してもらいます。

柊みみはなのどクリニック 院長 医師・内藤孝司さん
耳鼻咽喉科専門医。日本耳鼻咽喉科学会、耳鼻咽喉科臨床科学会、口腔咽頭科学会、日本東洋医学会、日本アレルギー学会、小児耳鼻咽喉科学会所属。「居心地が良く、患者さんに優しいクリニックをつくり、少しでも地域の役に 立ちたい」という思いから、1999年に同院を開院。
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠時無呼吸症候群は睡眠に関係する呼吸障害のひとつで、SAS(Sleep Apnea Syndrome)とも呼ばれています。ただのいびきだけなら問題ありませんが、睡眠中に呼吸が止まっている状態(10秒以上の気流停止)が「ひと晩で30回以上」もしくは「1時間あたり5回以上」ある場合を睡眠時無呼吸症候群とみなし、潜在的な患者数は日本だけでも300万人以上と推測とされます。
しかし、睡眠中に症状が出るため発見されにくく、実際にクリニックなどで治療している人はその2割程度だと言われています。
睡眠時無呼吸症候群のリスク

睡眠時無呼吸症候群は、いびきだけが問題の病気ではありません。自覚症状がないまま、無呼吸によって 睡眠の質が低下し、睡眠不足となることも。それを加齢や過労による慢性疲労だと放置してしまうと、命にかかわる病気や事故の原因になったり、集中力が低下して生活に支障が出たりすることもあります。
交通事故のリスク
睡眠時無呼吸症候群になると、突然の耐えられない眠気に襲われ、命に支障をきたすような大事故を引き起こす可能性があります。日常的に車やバイクの運転をする人は特に注意が必要です。
生活習慣病など、合併症のリスク
睡眠時無呼吸症候群を放置していると、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を発症しやすくなるだけでなく、病気の治療をしても十分な効果が得られないこともあります。また、いびきや無呼吸症候群によって低酸素状態を繰り返すため、心不全、不整脈、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)を発症するリスクも高くなります。
こんな症状がある人は要注意!

睡眠時無呼吸症候群の人に多い症状を下記にあげてみました。当てはまるものがあるかチェックしてみてください。
□ いびきをかいた後、呼吸が止まる(無呼吸)※家族や同居人からの指摘
□ 夜中によく目が覚める
□ 朝起きた時に、喉の渇きや頭痛がある
□ 十分に睡眠をとっているはずなのに、疲労感が残る
□十分に睡眠をとっているはずなのに、 集中力が続かない
□ 十分に睡眠をとっているはずなのに、昼間、頻繁に眠くなる
2タイプの睡眠時無呼吸症候群

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)
一般的に睡眠時無呼吸症候群という場合は、こちらの「OSAS」を指します。「OSAS」になると気道(喉の空気の通り道)が極端に狭くなる、もしくは完全にふさがってしまうことで、いびきや無呼吸が起こります。
・肥満(あごや首に脂肪がついている)
・扁桃腺の腫大(しゅだい)
・あごが小さい
・舌が大きい
・その他、顔の構造学的異常
原因の多くは肥満とされているため、ダイエットによって症状が緩和する人もいます。ただ、日本人の睡眠時無呼吸症候群の場合は、やせ形であごが小さい人にも多いのが特徴です。あごが小さいと上気道が狭くなるため、睡眠時無呼吸症候群になりやすいとされています。他にも、閉経後の女性や高齢の人でも発症しやすくなります。
中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)
こちらは睡眠時無呼吸症候群の人の中でも数%という珍しいタイプです。「CSAS」の場合、気道は狭くなりませんが、脳から呼吸筋への指令が出なくなってしまい無呼吸を引き起こします。発症にはいろいろな要因がありますが、一般的に心臓の病気を抱える人に多いとされています。
医師に相談し、適切な治療を

これまでのような症状に心当たりがある人は、医療機関を受診し、検査することをおすすめします。その上で、「睡眠時無呼吸症候群」と診断された場合は、重症度や原因、体の状態に応じて適切な治療を受ける必要があります。睡眠時無呼吸症候群の治療として代表的なものは次の通りです。
CPAP(経鼻的持続陽圧呼吸)療法
鼻に装着したマスクから気道内に適切な空気を送りこみ、閉塞した気道を圧力で広げることで呼吸を楽にして、睡眠中の無呼吸を改善します。睡眠中の無呼吸やいびきが減少し、よく眠れるようになり目覚めもすっきりします。
対象者:中等症から重症
口腔内装置治療(マウスピース)
マウスピースを装着することで、下あごを固定し、睡眠中に気道が塞がるのを防ぎ、呼吸を楽にします。個人差はありますが、呼吸の回数が装着前の半分以下になることを目標とします。
対象者:軽症から中等症、CPAP治療が困難な人
舌下神経刺激療法
睡眠中に舌の筋肉を支配する舌下神経を電気的に刺激することで、気道を開いた状態に保つ新しい治療法です。患者の胸部に電極を設置し、呼吸のリズムに合わせて舌下神経に微弱電流を流す装置を埋め込む手術を行います。
対象者:中等度~重度のOSAS患者でCPAPが使用できない人
最後に
昼間の眠気や起床時の喉の渇きなど、一見すると病気だとは思えないような症状の裏で、命にかかわる事態が進行しているのが、睡眠時無呼吸症候群の怖いところです。家族や友人などから、いびき・無呼吸を指摘されたら、まずは医師に相談してみてください。早期に治療を開始すれば、病気のリスクが下がり、睡眠の質も上がって、日中の体調が格段に上がるはずです。
診断には、専用の装置を用いた検査が必要となります。病院を選ぶ際には、ホームページなどを参考に、睡眠時無呼吸症候群の検査が出来るかどうかを事前に確認しておきましょう。
睡眠専門外来のほか、内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、循環器科、歯科・口腔外科、精神科などでも検査を受けられるところが増えてきました。いびきや無呼吸の症状が主体であれば、まずは耳鼻咽喉科や呼吸器内科を受診してみてください。
文:森下右子
この記事は「頼れる病院・クリニック2024-2025」(ゲイン刊)に掲載された記事をもとにしています。掲載内容は取材時のものです。