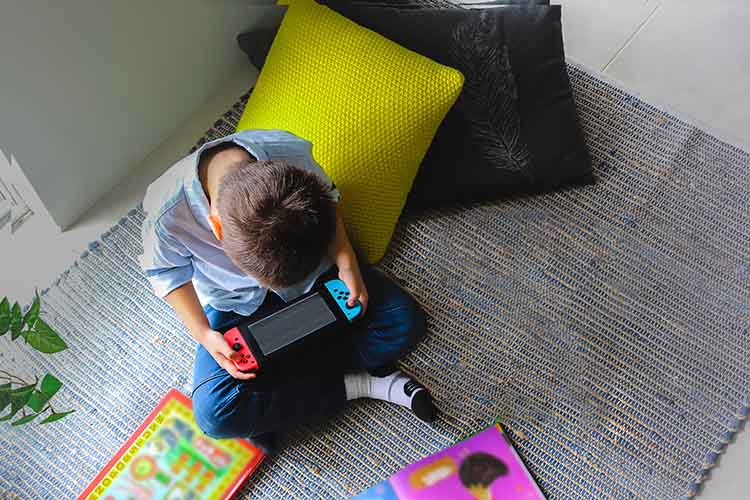「すべて思いどおりになる子育て」・・・そんなことって可能なの?と思ってしまいますよね。
市民と職員、企業が連携して立ち上げた『長久手子育て協力隊』※ このリリースイベントとして開催された講座では、キャリアコンサルタントの柴田朋子さんが、悩める親子のためのお話をされました。
「愛と不安を混同しない」「親の思いと子どもの思いを分ける」「家をひらく」など・・・「思いどおりになる子育て」とは、どのようなものでしょうか?
気になる講座の内容を、協力隊メンバーであり二児の父である筆者がご紹介します。
※長久手子育て協力隊
愛知県長久手市に、在住、在勤、活動をする子育て中の方、または子育てを支援したい方で結成された団体
キャリアコンサルタントの視点
柴田さんは、リクルート名古屋支社、瀬戸市役所でのキャリア教育事業担当を経てフリーランスのキャリアコンサルタントをされています。ご自分の仕事を「誰にでもある人生の岐路でのお手伝い」と表現されました。
大学の就職支援や社員研修で、悩み、迷うたくさんの人と出会うと、その人の子ども時代、親との関わりを考えさせられると言います。
- 柴田 さん
- 子どもの視点は『今』、「目の前のチョコが食べたい!」。
親の視点は『その先』、「もうすぐ夕食だからやめておきなさい」「虫歯になるからやめておきなさい」と言うことがあるでしょう。
キャリアコンサルタントの視点は、『もっと先』。その人が20代、30代になったときにどう自立するかを考えます。
「思いどおり」って誰の思い?

「親が子どもにこんなふうに育ってほしいと思うことは当然のことです。」
柴田さんのこんな言葉でお話はスタートしました。今持っている親としての思い、今日持ち帰りたいことなどを参加者同士で対話しました。
- A さん
- 子どものやりたいことを尊重しようと思っていても、自分に余裕がないとダメ、と言ってしまう。余裕があれば見守れる。僕はブレブレです。
- B さん
- 父親である僕の思いと、母親である妻の思いにもずれがあります。夫婦のコミュニケーションが大事だと痛感しています。
- C さん
- 子どもにいろいろ言いたくなるときもあるけれど、怒るのは自分が疲れちゃうし、親子関係が悪くなるほうが良くないと思うから放っておいています。
他の方のお話に、あるある、とうなずくことばかり。子どもにはのびのび育ってほしいと思っている私。薄着に裸足で公園を走り回り、自分の身長ほどの段差を跳び降りる次女を見守りながら、どこまで行動を制限すれば良いのか迷います。
それは本当に愛?
ある大学生は、営業職に就きたいと思いながら、保育士になることを応援してくれたお母さんを裏切れないと悩んでいます。
ある小学生のお父さんは、「子どもがテーマを決める夏休みの自由課題」のテーマを自分で決めてしまいます。
ある両親は、映画の専門学校に行きたいと言う息子を、無理やり大学に行かせます。
これらは、先生が実際に出会った親子の事例です。
- 柴田 さん
- どの親も、子どもに幸せになってほしいと願っていることは確かです。でも、これらは本当に愛でしょうか。子どもに「恩返ししないといけない」と思わせるものは愛でしょうか。親自身の不安ではないでしょうか。
親の不安が子どもを枠にはめる

- 柴田 さん
- 親が不安になるとき、「ピアノが上手だからそれを生かして安定した仕事に」「良い大学を出て大企業に就職すべき」といった親自身が分かる解決策に当てはめようとしてしまいがちです。親は子どもよりも経験が多く、今はありとあらゆる情報を手に入れることもできます。人に迷惑をかけない、失敗しない選択肢がどれか、親には当然分かります。
しかし、その枠の中に子どもを閉じ込めることは子どもの幸せにつながりません。親が不安を解消するだけです。子どもは子ども、私は私。それぞれに思いを持った別の人間で、別の人生を生きるということを忘れてはいけません。親の考える枠におさまる子が、親を超えていくことはないのです。
「ときどきでいいから、自分の思いと子どもの思いを分けているのか、考える時間を作りましょう。」と、柴田さん。
元気いっぱいの姉妹を持つ私の場合、子どもの行動にダメ、と言うとき「ちゃんとしつけができていない親だと思われるのではないか」という不安が隠れているような気がします。
とはいっても親は不安

参加者同士の対話の時間が取られました。対話の中で出てきた心配事に、柴田さんが答えました。
Q.中学生のゲームの時間をどの程度制限したらよいでしょうか。
- 柴田 さん
- 子どもにとっては面白いものなのでしょうね。たとえば「睡眠時間の確保」「食事は家族みんなで」といった家庭のルールを決めて、それを守れば良いのではないでしょうか。親が感情的に嫌というのとは分けたら良いと思います。また、子どもがルールに不満があると交渉してきたら、それに応じて話し合いをし、ルール改正をするのも良い経験になるでしょう。親が感情的になってぶれないことが大切だと思います。
Q.子どもが習い事を辞めたいと言い出したとき、どのように対処したらよいでしょうか。
- 柴田 さん
- 「すぐに辞めたら忍耐力がつかない」とよく言われますが、そんなことはありません。我慢することが良い、だけを伝えることが「自分の意見を言えない子」につながります。嫌なことは嫌と言えるのってすごいことですよ。大人になって困ったときに「助けて」と言えるようになります。「人に迷惑をかけるな」とよく言われますが、助け合いは迷惑をかけあうことです。
Q.子どもの趣味で、仕事につながりそうなものがあるとそちらへ誘導しがちです。そうすると子どもが興味を失うこともあるようで・・・。どうしたらよいでしょうか。
- 柴田 さん
- 大人は将来役立つことをさせたいと考えますよね。でも、何が将来役に立つかなんて誰にも分かりません。英語が役に立つのか、プログラミングが役に立つのか、当たるも八卦、当たらぬも八卦です。子どもよりも大人が知っている分、先を見通せるのは当たり前です。だからといって、子どもが自分で考えて動く力を奪っていい理由にはなりません。子どもが予想したとおりに失敗しても「だから言ったじゃん」は言わないようにしています。
子育ての答え合わせはずっと先
- 柴田 さん
- 就職まで見届けることが親の仕事だと言う人もいますが、答え合わせはもっと先です。大人になってからも社会に育ててもらえます。そのために必要な、人に可愛がられる力、人と助け合える力を育てることはできます。
その方法は「家をひらく」ことです。家をひらき、いろいろな人と出会える場にすることで、子どもの力はどんどん伸びます。子どもの持つすごい力を、閉じ込めないでください。
「子どもが○○できない」と悩んだとき、きっとそこには自分の不安があります。子どもを思いどおりにすることはできません。でも、自分を思いどおりにすることはできます。親自身が自分の人生を楽しく生きていくことが大切です。
最後に

自分の子育てに自信の持てない私ですが、「子どもはすごい力をもっているから親の枠に閉じ込めないで」「親は自分を生きて」という柴田さんのメッセージに励まされました。
一方で、子どもと親の思いを分けることや家をひらくことは簡単なことではないとも思います。核家族世帯ではどうしても親子の距離は近くなります。地域のつながりは希薄で、子どもがたくさんの大人に出会う機会も減っています。
子どもをたくさんの大人で育てる場、親が不安になったときに話して楽になる場づくりを実現するのが、長久手子育て協力隊の使命なのかもしれません。今後の活動にご期待ください。
文・写真:Hiroki&Shino

筆者:Hiroki&Shino
長久手子育て協力隊員。
育休中の父ちゃん(学校の先生)と長久手市職員の母ちゃんです。7歳と2歳の姉妹を育てています。
あわせて読みたい