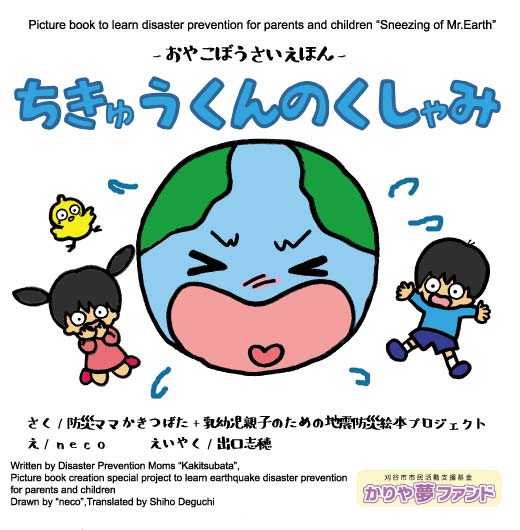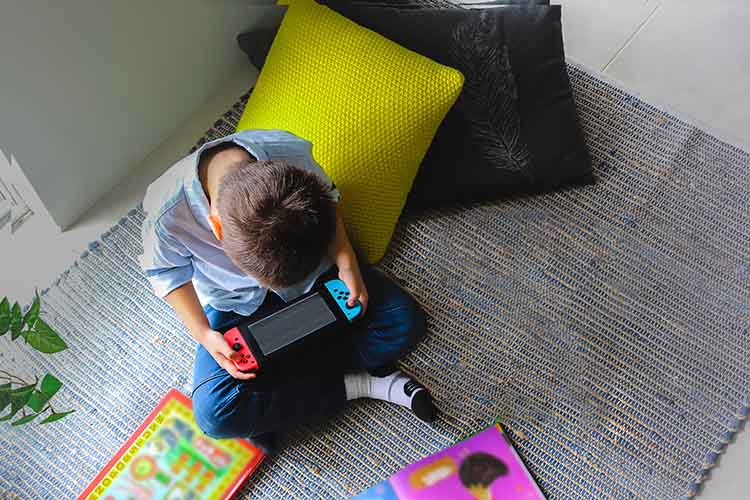9月1日は、毎年『防災の日』に制定されています。子育て中のママやパパは、毎日子どものお世話や家事、仕事で忙しくて精一杯ですよね。そんな中で、もし災害が起きたら?正直、想像もつかないし、考えたくないかもしれません。今回は、名古屋大学減災連携研究センターで「親子の防災」について研究をする蛭川さんにお話をうかがいました。

地震や台風などの自然災害は必ず訪れるものです。必要以上に恐れるのではなく、家族や友達、みんなで防災について話してみましょう。
防災の日とは?由来や意味は?
9月1日の『防災の日』は、1923年に関東大震災が起きた日であり、毎年台風がやってくるシーズンでもあります。
日本は、地震や台風だけでなく、豪雨・洪水など、自然災害が多いため、災害に対する意識を高めることを目的に、防災の日が制定されました。
保育園・幼稚園・学校や会社などでは、このタイミングで防災訓練がおこなわれるところも多いのではないでしょうか。
防災訓練では、災害が起きたときに不安や焦り、パニックなどで動けなくなってしまうことがないよう、避難までの一連の動きを確認します。家庭でも同様に、災害に備えて準備をしておきましょう。
おうち防災、まずは家具の固定!
 「固定ベルト×突っ張り棒」など、組み合わせると強度が増します。忘れがちな冷蔵庫もしっかり固定を。
「固定ベルト×突っ張り棒」など、組み合わせると強度が増します。忘れがちな冷蔵庫もしっかり固定を。
「防災」というと、水を備蓄して避難のためのアレを用意して、コレを用意して・・・ああ、何からやればいいの!となって、手が付けられなくなっている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に、優先順位第1位、まず最初にやって欲しいのは「家具の固定」です。
阪神大震災の時、ケガの原因(内部被害)の約50%が家具の転倒・落下でした。
L字金具、ベルト、突っ張り棒、ストッパーなど、さまざまな固定器具があります。
1つよりも、組み合わせて使うとより効果的です。
「壁に穴を開けなきゃいけないし・・・」「突っ張り棒ってダサいし・・・」その気持ち、よく分かります。確かにそうかもしれません。でも、安全を確保することが何より大切です。子どもと家族、自分自身を守るために、おうちの中をチェックして対策をしましょう。
子どもと一緒に話し合おう

東日本大震災の津波で多くの死者が出た宮城県名取市の閖上(ゆりあげ)地区で、54人の園児を無事に避難させた保育園があります。所長さんは、津波を想定した避難訓練や避難計画を事前につくっていたそう。渋滞する道路はどこか、子どもたちの避難先はどこにするか、など。そして、避難先でも、いつもと同じように一緒に歌を歌い、お絵かきをし、園児たちが大きなパニックになることなく過ごしたとのこと。
愛知県刈谷市の現役ママたちがつくった、親子向けの防災絵本「ちきゅうくんのくしゃみ」というのがあります。
地震、津波、豪雨、台風・・・自然災害は怖いけど、地球はくしゃみを繰り返して、今の形になっています。怖がるだけではなく、しっかり話し合って対策することが大切。特に小さなお子さんに関しては、楽しみながら防災を身近に意識し、準備ができることが理想です。
年に1回、防災の日はやってきます。避難リュックの見直しはもちろん、子どもも成長とともに、幼稚園・保育園から小学校に上がるなど、生活環境が変わります。毎年この日を、持ち物の確認や、親子で防災について話し合える日にできるとよいですね。
- 家の中でどこが一番安全?
- 避難場所はどこにする?
- 避難バッグはどこに置く?
- 連絡はどうやってとる? など
自然災害、特に地震はいつ起きるかわかりません。時間帯やそのとき誰が家にいるかなど、色々なケースを想定し話し合っておきましょう。
みんなで避難バッグをつくろう!

「ウチは免震マンションだから」「内陸に住んでいるし」など、なんとなく自分だけは大丈夫な気でいる人はいませんか?大事なのは「自分ごと」として考えて、備えること。
首都直下地震が東京で起きた場合、ライフラインの復旧目標日数は、電気6日、上水道30日、ガス55日となっています。(内閣府発表の想定)
救援物資もすぐに届くとは限りません。お店にも人が殺到し、必要なものが手に入らなくなる可能性もあります。
被災地のヒアリングをしても「アレルギー対応の非常食がなかった」「子どもの好きな食べ物がなくて、全然食べてくれなかった」「おじさんから生理用ナプキンを1つしかもらえなかった」などの声があがっていました。
一方で「救援物資の中にキャラクターの絆創膏があって、子どもが元気になった」という声も。大変な時も、お気に入りのものがあるだけで、元気になれます。
「もし、数日間避難生活をするとしたら?」を想定し、旅行にいく感覚で、家族みんなで避難バッグを用意してみてはいかがでしょうか。
備蓄は「ローリングストック」で
 非常食・保存食には子どもの食べやすいものも入れておくようにしましょう。
非常食・保存食には子どもの食べやすいものも入れておくようにしましょう。
非常食や保存食を用意しても、賞味期限が切れてしまう・・・そんな時におすすめなのが「ローリングストック」と呼ばれる方法です。
- 缶詰、フリーズドライ食品、カップ麺などの食材を少しだけ多めに買い置きする。
- 1ヶ月に1回など、定期的に賞味期限の近いものから順に食べる。
- 食べた分だけ買い足しをする。
非常食や保存食も普段から食べていなければ、もしもの時にどうすればよいか分からなくなってしまいます。ひょっとしたら、子どもの口に合わず食べられない可能性もあります。
日頃からの防災意識を高めるためにも、ローリングストックを取り入れることをおすすめします。
最後に
災害時には、普段の子育てに上乗せ労働が加わります。今までの生活が送れないために起きる家事の上乗せ、事務手続き、さらには災害によるストレスも。さまざまな被災地での調査をおこないましたが、子育て世代へのケア体制は十分ではないのが現実です。
忙しい日々の中、後回しになってしまいがちですが、普段から防災の意識をもち、いざというときに動けるよう、子どもと一緒に準備を進めておきましょう。
知って、備える「減災館」
名古屋大学東山キャンパスにある「減災館」では、地震や津波などの災害を想定した再現装置や、最先端の防災・減災の展示がされています。ここでは、災害による被害を減らし、早期復旧のための研究がおこなわれ、産官学連携・地域連携に中部電力も加わっています。
新型コロナウイルス感染症対策のため、完全予約制にて開館しております。
減災館の見学・利用についてはこちらをご覧ください。
(2022年7月26日現在)

名古屋大学減災連携研究センター
エネルギー防災(中部電力)寄附研究部門特任助教
名古屋大学大学院工学研究科修了、専門はコンクリート工学。中部電力では送変電技術センター土木建築課で工事を担当。減災連携研究センターに出向し、エネルギー防災・減災の研究をおこなう。一児の母である視点から、パパママの備災連携についても調査・研究・啓蒙活動をすすめている。
文:三輪田理恵