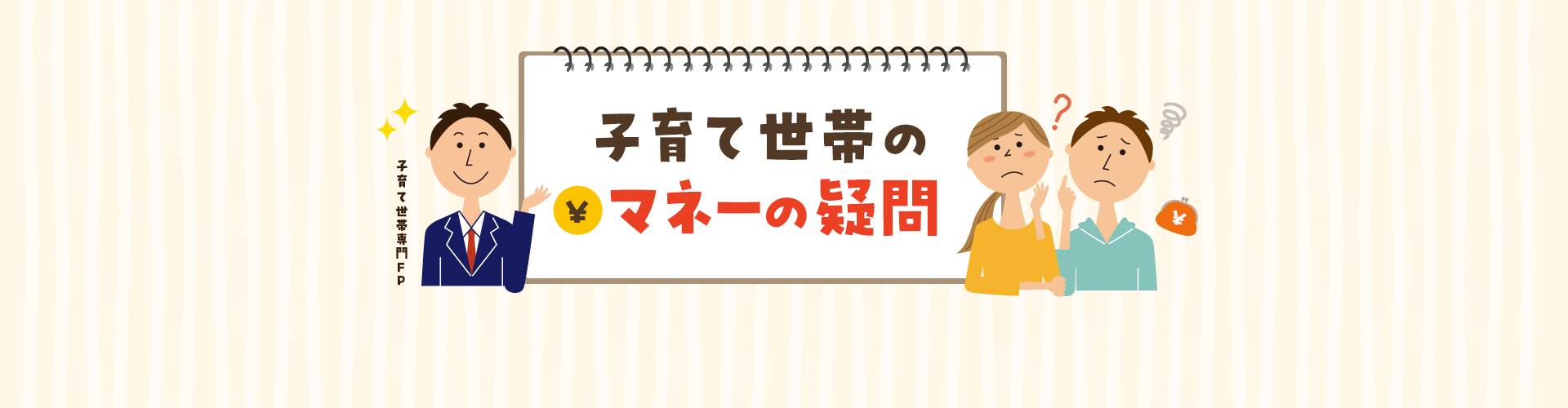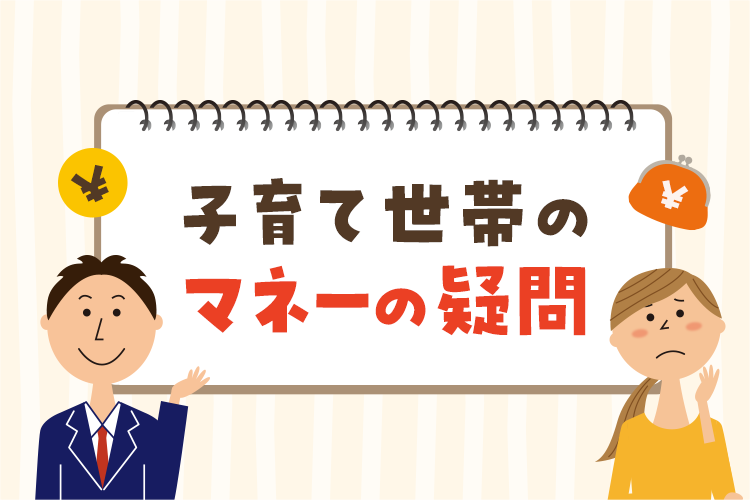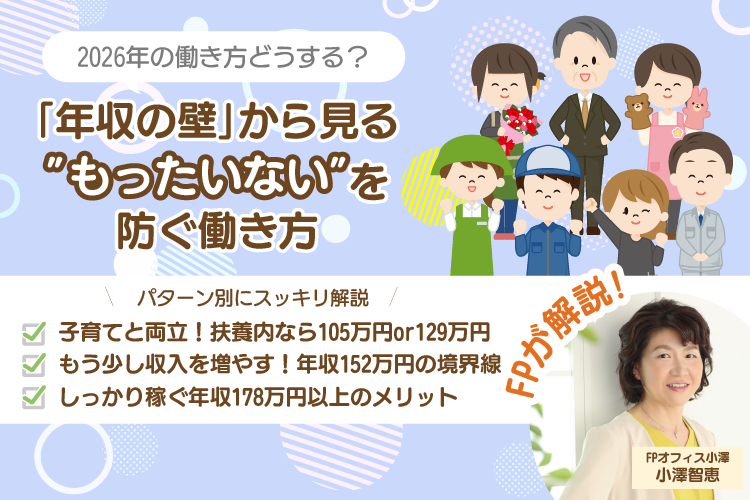高齢の親に介護が必要になったら、費用は本人の資産でまかなうのが原則です。しかし、頼りにしていたその資産が、凍結されて使えなくなってしまうことがあるんです。親の年金、定期預金が動かせず、実家や株式の売却が出来なくなってしまったら……。
こうしたリスクを避けるため、家族による財産管理の1つとして「家族信託」があります。ここでは、家族信託に詳しいファイナンシャルプランナーに、その仕組みとメリットについて聞きました。

FP事務所RAC代表 近藤賢一(こんどう・けんいち)さん
南山大学経済学部卒業後、求人広告営業や人材あっせん事業のコンサルタントなどを経て、FPとして独立。年間100世帯以上の家計相談や資産形成に関するアドバイスを行っている。小学校PTA会長でもあり、Youtubeチャンネル「教えて!こんけん先生」では、子どもへの金融教育に関する動画を配信中。
口座凍結、不動産取引の制限とは

ある日突然、年老いた父母の口座からお金が動かせなくなった。認知症の父母との同居を機に、空き家になった実家を売却しようとしたら、できないと言われた……。実はこうした例は珍しくありません。
銀行は高齢者を守るために口座の凍結をすることがあり、多くの金融機関において、窓口などでの本人の状態から凍結の判断をしています。認知症などによる判断能力の低下により、詐欺や本人による誤操作、家族間のトラブルなどリスクが高まるためです。
また、判断能力が不十分と判断された場合、不動産の取引が制限される場合もあります。高齢社会が進行する現在では、資産が本人の望まない形になるのを避けるため、高齢者を守るために、こうした制限が設けられています。
親族であれば取引は出来ると思うかもしれませんが、制限を受けた場合は基本的にNG。年老いた親が生活費を引き出せなくなったり、あてにしていた実家の売却益が介護費用に充てられなくなったりしたら、資産の取引制限は高齢者を抱える家族にとって死活問題です。
資産を守る家族信託とは

親が認知症などになってしまい、判断能力が心配される場合は、成年後見人制度の利用を考えてみてください。これは認知症の人などを支援し、生活や財産を守る仕組みで、家庭裁判所に申し立てて後見人を登記します。法的に保護されますが、誰を後見人とするかが難しく、本人が亡くなるまで後見人には報酬の支払いが発生するなど、金銭的な負担も少なくありません。
では、親が認知症になる前にどんな手立てが打てるのでしょうか。その1つの方法が家族信託です。これは家族の誰かが本人と信託契約を結び、財産を管理できるようにする制度です。後見人の選定や支払いが発生せず、家族が責任を持って柔軟に対応できることがメリットです。高齢の父母の判断能力が心配になる前に、家族信託を検討してみるのも良いでしょう。
家族信託の手続きは
家族信託の契約を結ぶには、どうしたら良いでしょう。まず、本人の判断能力が確かなうちに、家族を交えて誰が契約を結ぶのかを決めましょう。そして、弁護士、司法書士、場合によっては、ファイナンシャルプランナーなどに相談してみましょう。銀行などの金融機関では、家族信託にあまり詳しくない場合があります。また、専門家でも家族信託に慣れていないケースがあるため、家族信託に詳しい相談窓口を探しましょう。
実際の契約においては、信託用の口座を用意して、家族が管理できる現金や株などを決めたり、土地や建物などを確認しておいたり、具体的に管理の範囲を見定めていきます。例えば不動産について、実家に住む人がなく空き家になった場合には、固定資産税の課税標準が6倍になることも。いつか売却や処分をしようと放っておくと、思わぬ費用がかかることもあります。こうした不要な負担を減らすためにも、空き家や不動産の売却を早めに検討し、その前の家族信託契約も選択肢に入れておいても良いでしょう。
もちろん、信託契約後も資産はあくまで本人のものであり、管理人のものになるわけではありません。管理中の勝手な使い込みはできず、本人の死後は平等な条件で相続へと移ります。当然のことながら、長男が信託契約をしたからといって、資産がすべて長男のものになるわけではないのです。
最後に
介護には予想外のお金がかかります。頼みの綱である親の資産が凍結されてしまったら、現役世代がその金銭的負担を負うことになってしまいます。だからこそ、相続対策の前に凍結対策を。家族信託は、家族が少ない負担で柔軟に介護費用を確保できる、大きな選択肢です。
文・聞き手:きずなネットよみものWeb編集部