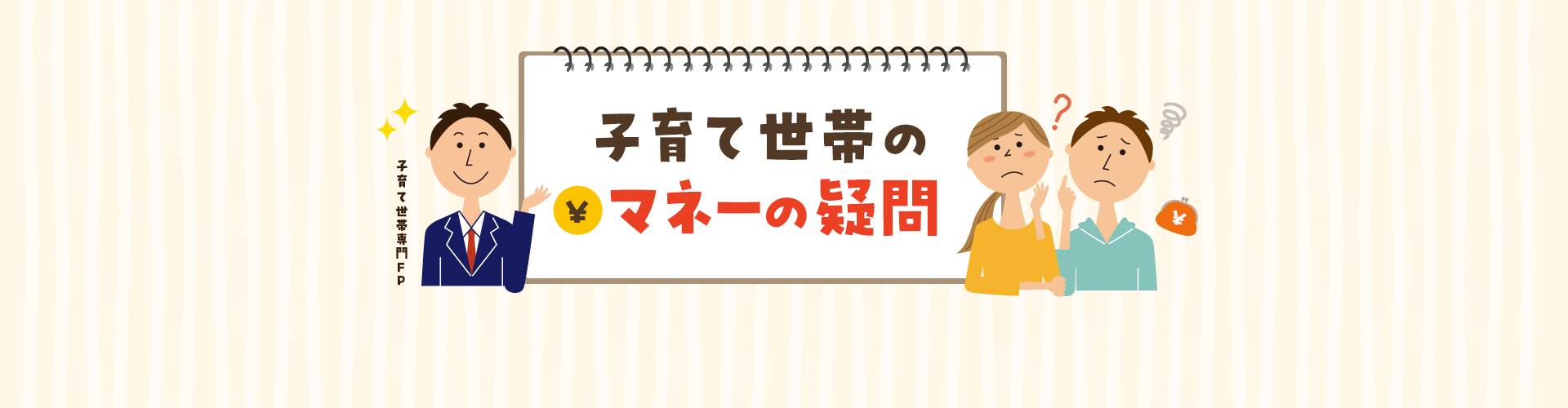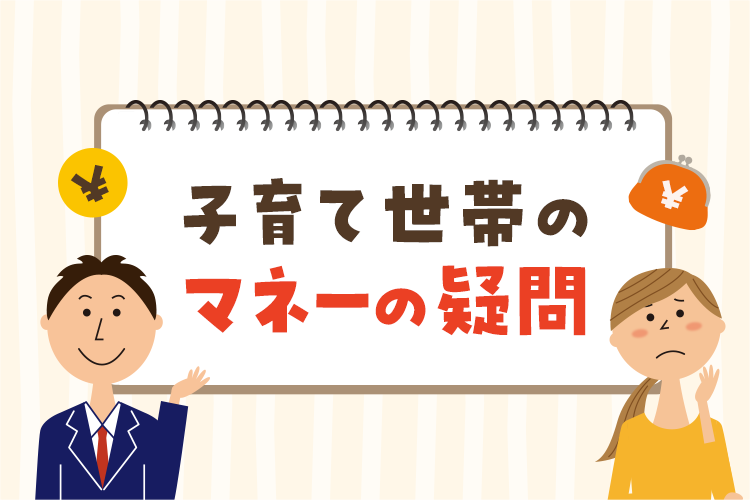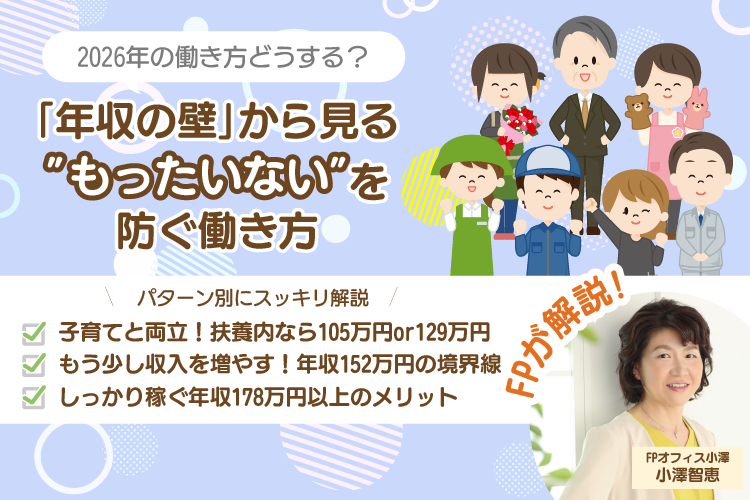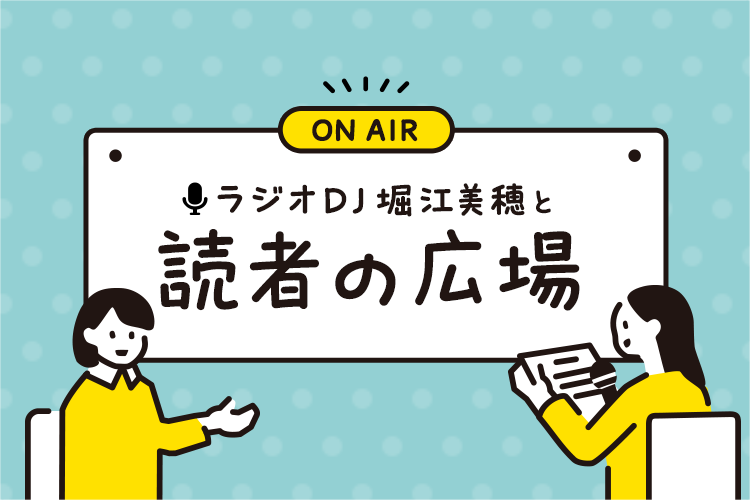2026年度から開始される、高校授業料の実質無料化。世帯年収に関わらず学費の負担が減るため、私立高校への進学がしやすくなると考えられます。一方、近年では中学受験も身近なものになり、私立の中高一貫校を目指す家庭も増えています。
子どもと家庭に合った学校を選ぶため、教育費に詳しいファイナンシャルプランナーに、中学・高校でかかる費用について聞きました。

FP事務所RAC代表 近藤賢一(こんどう・けんいち)さん
南山大学経済学部卒業後、求人広告営業や人材あっせん事業のコンサルタントなどを経て、FPとして独立。年間100世帯以上の家計相談や資産形成に関するアドバイスを行っている。小学校PTA会長でもあり、Youtubeチャンネル「教えて!こんけん先生」では、子どもへの金融教育に関する動画を配信中。
公立・私立の教育費の差は?

公立と私立ではどれくらい教育費が違うのでしょうか。ここでの教育費とは、授業料や施設使用料、学用品費、通学関連の費用、修学旅行費用のほか、塾や習い事など、学校外の教育にかかる費用なども含みます。
文部科学省が2023(令和5)年度に実施した調査によると、平均値は次のようになっていました。
中学:約54万円 高校:約60万円
<私立> ※年間金額
中学:約156万円 高校:約103万円
これを中学1年生~高校3年生までの6年間分に換算すると、公立中・高では約342万円、私立中・高では約777万円ということになり、公立と私立で約2.3倍の差があります。
もちろんこれは全国の平均値に過ぎません。施設使用料や学用品が高額であったり、学校が遠方で交通費がかかったり、また、寮などに下宿する場合など、特に私立中高の場合にはさまざまなケースが考えられるでしょう。
高校授業料無償化って?

このような高校の教育費の違いを受けて、国は2010年度に教育にかかる費用をサポートする「高等学校等修学支援金制度」を定め、2025年度には所得制限を撤廃しました。
公立高校に通う子どもを持つ家庭は世帯年収に関係なく、年額11万8800円が支給され、私立高校に関しては、世帯年収が590万円以下の場合39万6000円、それ以上の場合は11万8800円が支給されています。
さらに、2026年度以降は私立高校に関しても世帯年収に関係なく、授業料の平均額である45万7000円が支給される予定です。これによって、公立・私立ともに、高校の授業料が実質無料になります。
また、国の制度とは別に、自治体が個別に高校の学費を支援している場合があるので、ホームページなどで確認しておきましょう。
塾の費用は?
こうした費用の違いをふまえて私立中・高への進学を考える家庭も増えていると思います。その際、注意すべきなのが塾の費用です。中学受験を目指す小学生のほとんどが塾に通っており、その費用は少なくありません。
高校受験を選択する場合も、多くの中学生が塾に通います。受験が近づくと、授業回数を増やしたり、特別講習を受けたりすることも多く、中学3年間通うとそれなりに大きな金額になります。
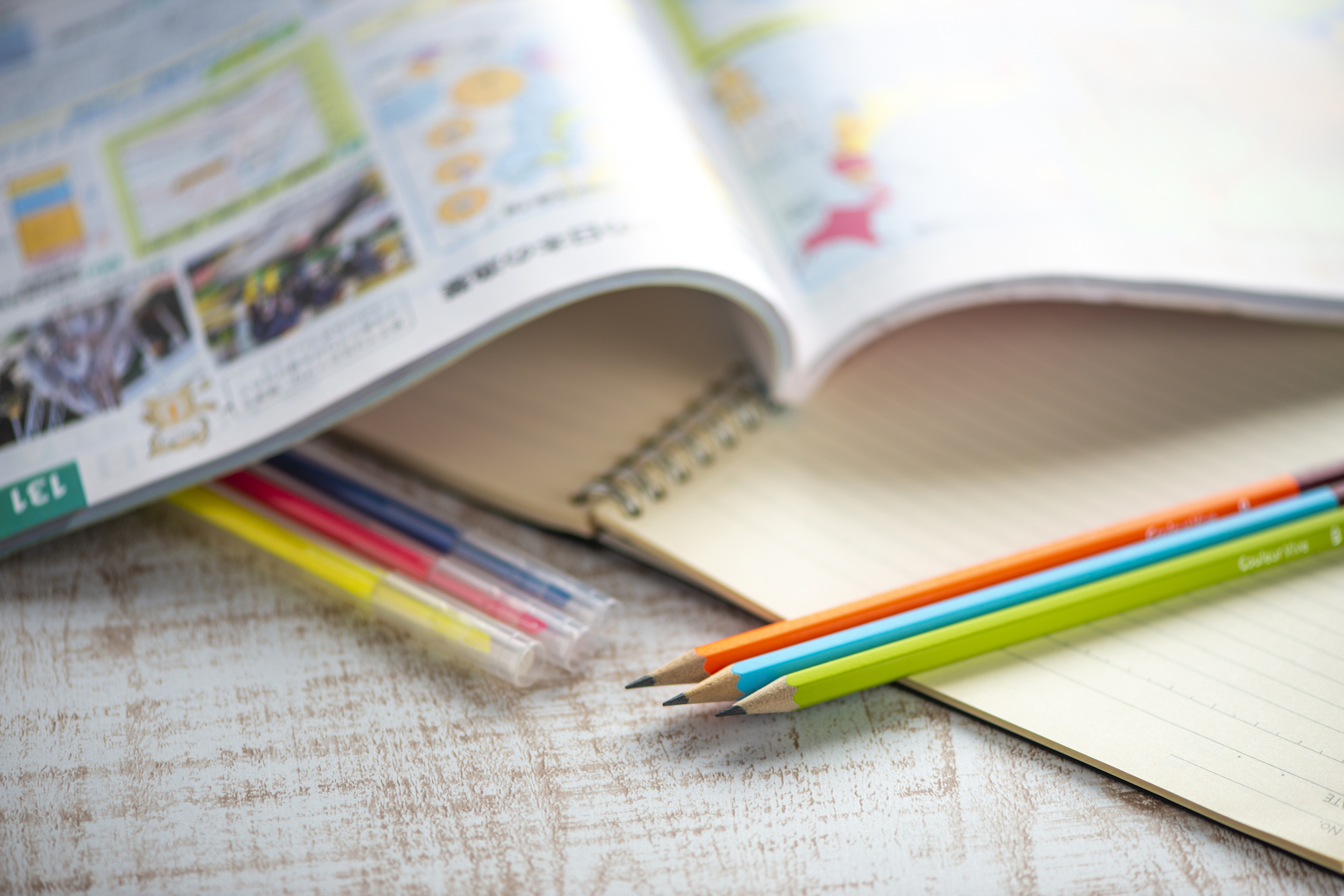
塾の形式やカリキュラムは多種多様で、一般的に大手の塾は個人経営の塾よりも費用が高く、個別指導は集団指導よりも高い傾向があります。また近年では、インターネットを活用したオンライン塾や学習アプリもたくさんあり、比較的安価で利用できます。子どもの性格や目的、予算などに合わせて、比較検討してみましょう。
足りない学費をまかなう方法は?
私立中・高に入学したくても、「どうしても学費が足りない」という場合もあるかもしれません。こうした場合には、奨学金を検討してみてはいかがでしょうか。それぞれに貸与条件はありますが、日本学生支援機構(旧日本育英会)のほか、民間団体の奨学金もいくつかあります。私立中・高で独自の奨学金や特待生制度を設けている場合もあるので、調べてみると良いかもしれません。
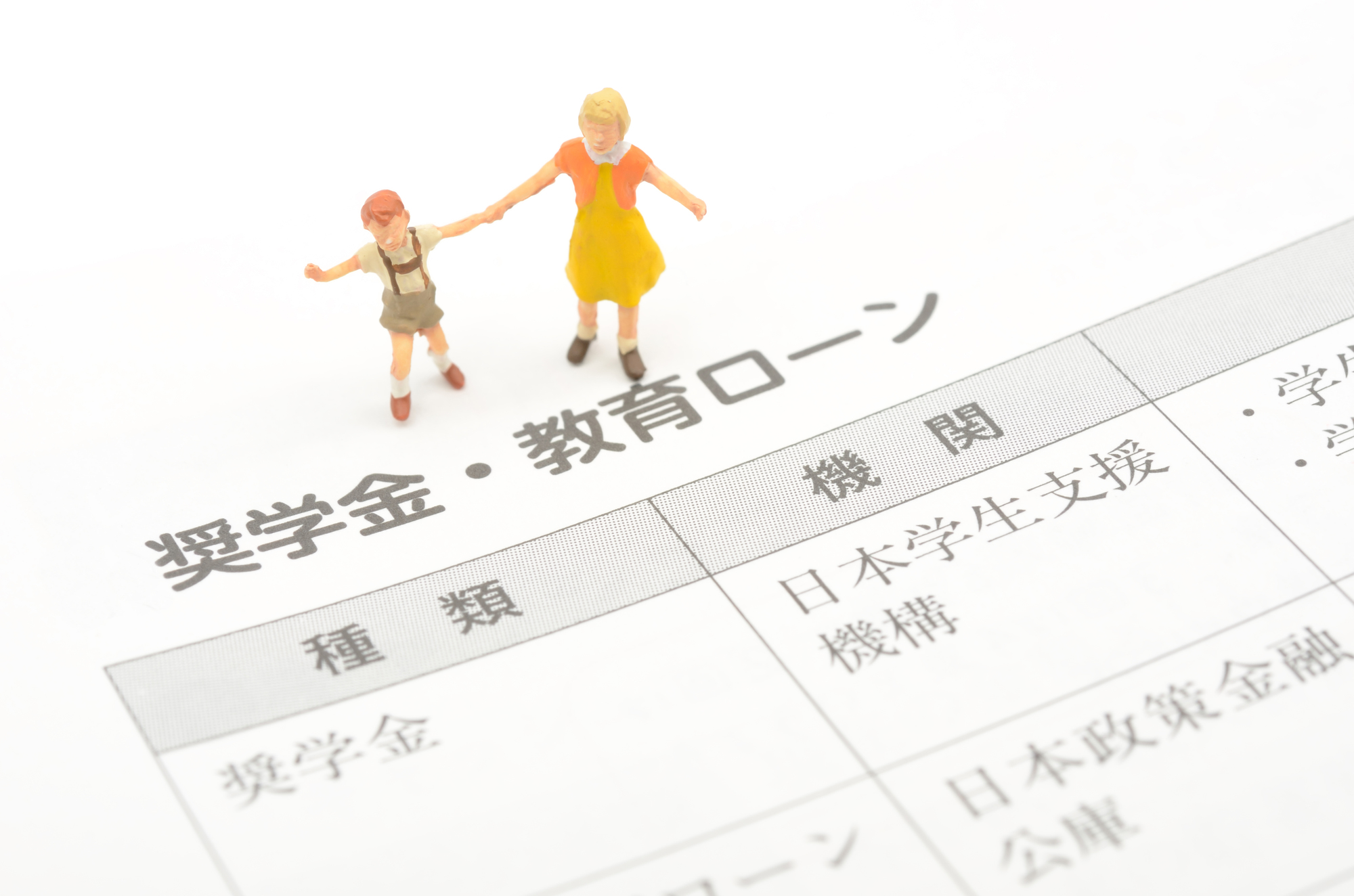
奨学金は学生本人が借りるものですが、保護者の名義で学費を借りるのであれば、教育ローンという選択肢もあります。日本政策金融公庫の教育ローンは、固定金利3.15%で350万円まで借入が可能(条件により450万円まで)。民間の銀行・金融機関の教育ローンだと、融資額の上限が高く、金利も比較的高めで変動するものもあります。学校と金融機関が連携している商品もあるので、検討してみましょう。
子どもの将来の教育資金として、学資保険を検討している家庭もあるかもしれません。しかし、学資保険の返戻率は、現在100〜105%程度。受け取り時期や金額の柔軟性も低いので、個人的にはあまりおすすめしません。将来に向けて学費を準備するのであれば、NISAや積み立て投資信託などを検討する方が良いでしょう。
最後に
子どもにより良い環境で学んでもらいたいと考えるのは、どの親も同じです。私立中学の存在が身近になってきた今、子どもにとってどんな環境が良いのかを今一度問い直してみましょう。同時に、家計における教育費についても、ロングスパンで点検してみると良いのではないでしょうか。
文・聞き手:きずなネットよみものWeb編集部
子育てとお金について、聞きたいことはありますか?
↓リクエストなど、「一言ボックス」からお寄せください↓