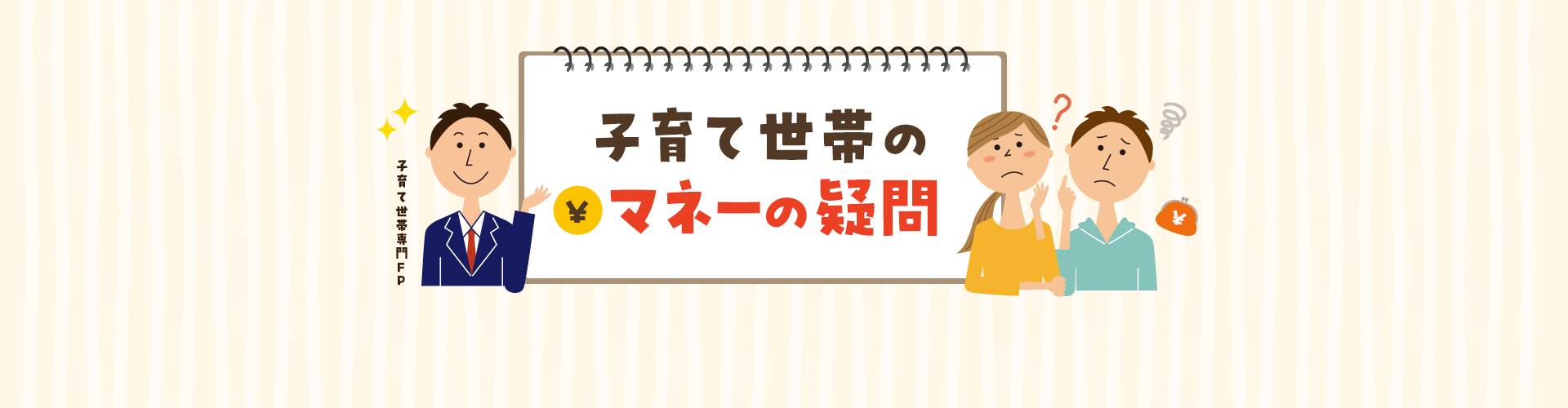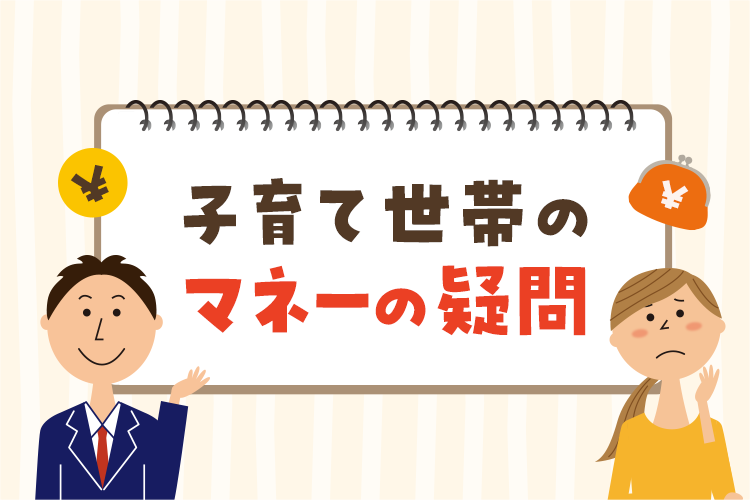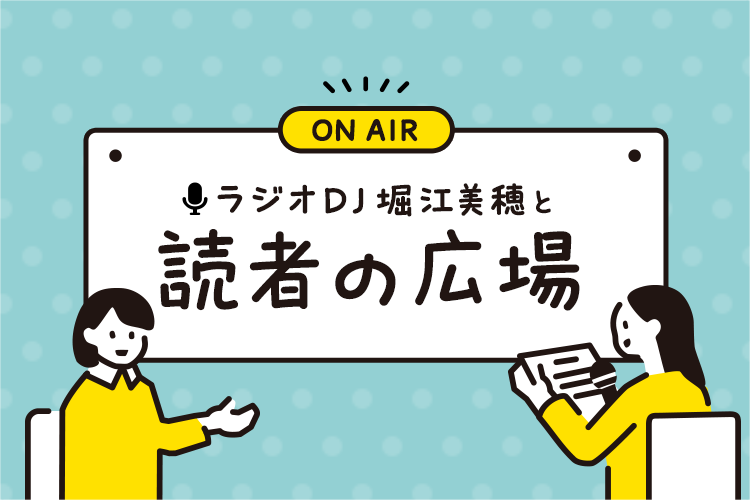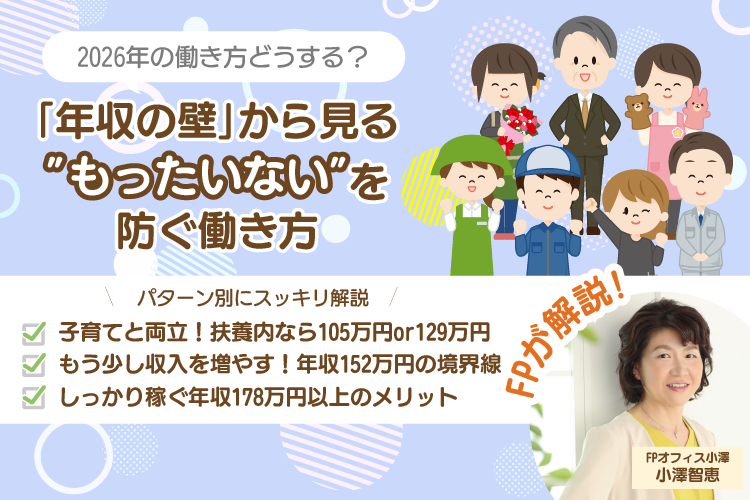今月から新連載「子育て世帯のマネーの疑問」をスタート! 子育て世帯のお金にまつわるお悩みに専門家がお答えします。
2024年3月、名古屋市内に住む小学生が友人からだまされて、93万円を払ってしまったという事件が話題になりました。これほど高額なケースは珍しいですが、実は子ども同士のお金のトラブルは非常に身近なものです。特に、貸し借りを通じて問題が起こる例は少なくありません。
どんなトラブルがあるのか、問題を防ぎ解決するにはどうしたら良いのか。子育て世帯専門のファイナンシャルプランナー(FP)で、「子どもと大人のお金の先生」として活躍中の近藤賢一さんに聞きました。

FP事務所RAC代表 近藤賢一(こんどう・けんいち)さん
南山大学経済学部卒業後、求人広告営業や人材あっせん事業のコンサルタントなどを経て、FPとして独立。年間100世帯以上の家計相談や資産形成に関するアドバイスを行っている。小学校PTA会長でもあり、Youtubeチャンネル「教えて!こんけん先生」では、子どもへの金融教育に関する動画を配信中。
親が知らないお金の貸し借り

子どもの間でも、お金の貸し借りからトラブルが起こることがあります。「おこづかいが少額だから大丈夫」「お金を使う場面は少ないから、そんなはずはない」と思っているのは、親だけかもしれません。
小学校高学年から貸し借りが増える
お金の貸し借りが増えるのは、主に小学校高学年から。おこづかいを自分で管理できるようになり、友達と近場に遊びに行く機会も増えてくる時期です。また、塾や習い事で長い時間を過ごす友達ができ、飲み物代などを持って出かけることもあるでしょう。そうした中、友達同士でお金の貸し借りが発生する機会が出てきます。
貸し借りは、どんなシチュエーション?
まず多いのは、お菓子やジュースを買う時。コンビニや自販機などを利用する際に、少額を借りるケース。中学生くらいになると、子どもたちだけで映画館や遊園地などに遊びに行き、交通費や入場料を払う際、貸し借りが発生することもあるでしょう。
さらに中高校生になると、文房具や学用品が必要になったり、無くしてしまったりした時に、校内の購買やコンビニでとっさにお金を借りることもあり得ます。財布の紛失や忘れ物をしてしまった時、友達から借りたお金で過ごすこともあるかもしれません。
さらに、お年玉やおこづかいをもらったタイミングで、友達同士の話の流れから貸し借りをしてしまうことも。最近では、現金のやり取りだけでなく、ゲームなどオンライン上の課金に対して、プリペイドカードやギフトコードを使った貸し借りも発生しています。
貸し借りからトラブルに?!
お金の貸し借りは、子ども同士のトラブルにつながりがちです。例えば、最初はお菓子や文具代など、少額だったとしても、繰り返すようになったり、金額が増えていったりすることがあります。一体いくら貸したのか分からなくなって、貸した側・返す側の認識が一致しない場合も。また、金銭の貸し借りを発端に、利息や見返りを求めるようになることすらあります。
そもそも子ども同士だと、お金を返すのを忘れてしまいがち。一方で貸した側も返金の催促は非常に難しいので、大人以上にトラブルに発展しやすいのです。こうしたトラブルが重なって、いじめにつながることも珍しくありません。
お金の教育でトラブルを予防

こうしたお金の貸し借りにまつわるトラブルを避けるためには、事前の教育が重要です。小学校の低学年や、子どもにおこづかいを渡し始めるタイミングで、お金の管理の仕方や貸し借りのリスクについても教えてあげましょう。
また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった時には、すぐに親に相談するように伝えましょう。普段から親子でお金の話をし、一緒に学ぶ姿勢を持つことで、子どもはトラブルを隠さず、親に相談してくれます。「お金で困ったことや不安なことは必ず相談してね」と念を押し、「家庭ごとに考え方が違うので貸し借りはやめよう」「最後に守れるのは親だけだよ」と伝えましょう。そして、子どもには「大人の許可なしにはお金の貸し借りをしてはいけない」という認識を身につけさせましょう。
最後に
「自分の子どもに限って、お金の貸し借りやトラブルはない」「うちの子はしっかりしているから大丈夫」と思いがちですが、過信は禁物。子どもは非常に未熟な認識のもとで、親が思う以上に貸し借りをしています。まずはその前提を認識し、早めにお金やその貸し借りについて話せる環境をつくり、大きなトラブルを未然に防ぎたいですね。
文・聞き手:きずなネットよみものWeb編集部