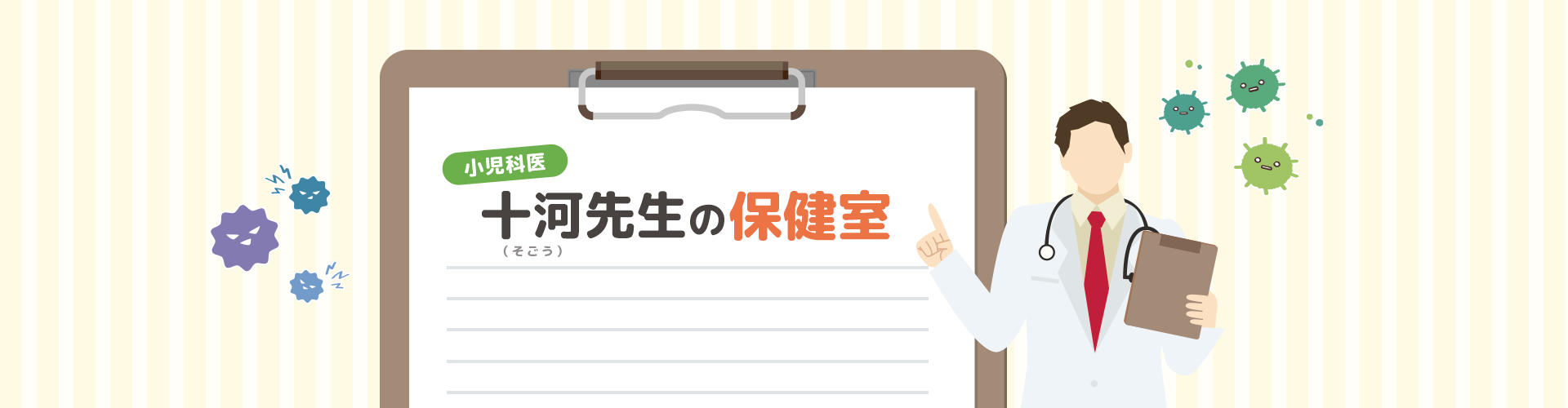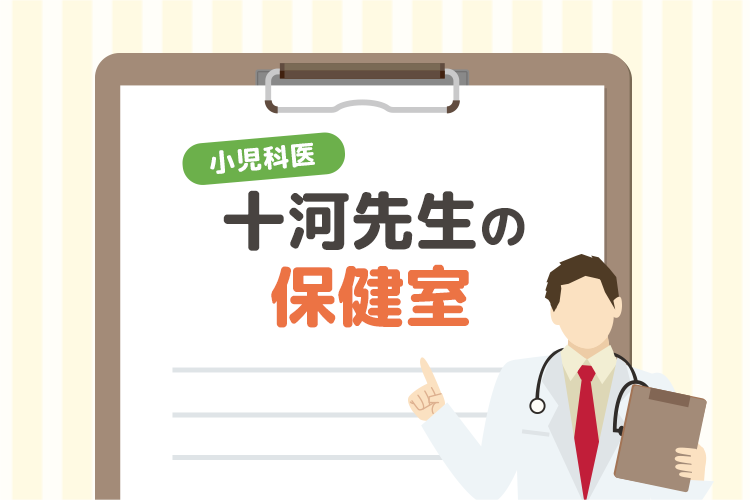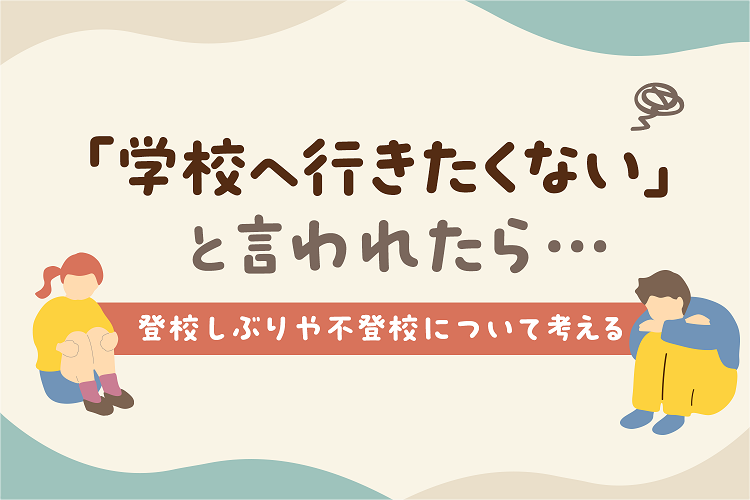子供が朝なかなか起きられない、頭痛や腹痛を訴えるなどがあると「学校に行きたくないから?」と思われるかもしれません。しかし、もし続くようなら「起立性調節障害」の可能性もあります。
保護者の多くは、ゲームやスマホへの依存症、夜更かし、学校嫌いなどが原因だと考えて、怒ったり、朝に無理やり起こそうとしたりすることも。「怠けているのは?」と疑うことで、親子関係が悪化してしまうこともあります。
今回は、小中高生に見られる「起立性調節障害」の特徴や症状、原因、治療法について解説していきます。

筆者:十河剛 (そごうつよし)
済生会横浜市東部病院小児肝臟消化器科部長。小児科専門医・指導医、肝臓専門医・指導医、消化器内視鏡専門医・指導医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。
診療を続けていく中で、“コーチング”と“神経言語プログラミング(NLP)”と出会い、2020年3月米国 NLP&コーチング研究所認定NLP上級プロフェッショナルコーチの資格を取得、2022年全米NLP協会公認NLPトレーナーとなる。また、幼少時より武道の修行を続けており、現在は躰道七段教士、合気道二段、剣道二段であり、子供達や学生に指導を行っている。
「子供の一番星を輝かせる父親実践塾」Voicyにて毎朝6時から放送中。
動画セミナー『子供の天才性をハグくむ叱らなくても子供が勝手に動く究極の親子コミュニケーション術』
起立性調節障害とは?

起立性調節障害とは、自律神経のバランスが崩れることによって、たちくらみ、意識を失う、朝起きられない、だるい、胸がドキドキする、頭が痛いなどの症状を訴える病気で、思春期によくみられます。
以前は「心と体の成長による思春期の一時的な体調不良で思春期を過ぎるころには良くなる」と言われていました。しかし、最近の重症例では、日常生活が送れなくなり、長いこと学校に行けなかったり、部屋に引きこもったりして、学校生活やその後の社会復帰に大きな支障となることがわかってきました。
このような重症例は約1%ですが、軽症例を含めると小学生の約5%、中学生の約10%に起立性調節障害がみられます。不登校の約3~4割に起立性調節障害があり、10~16歳頃、特に女子に多い傾向があります。また、約半数に遺伝傾向があるといわれています。
起立性調節障害の症状は?

立ちくらみ、朝起きられない、気持ち悪い、だるい、気を失う、頭痛などがあります。私の外来では、腹痛や吐き気を訴えて受診し、体を調べても原因がわからず、最終的に起立性調節障害と診断することも少なくありません。
症状としては午前中に強く、午後には良くなるのが特徴。起き上がると、症状が強くなるため、ベッドでずっと寝ている子もいます。夜になると元気になり、スマホやゲーム、テレビができるようになるので、サボっている、怠けていると誤解されることもあります。
夜には目がさえて眠れずに、朝はなかなか起きられずに、ひどくなると昼夜逆転の生活になってしまうことも。いつも顔色が悪い、乗り物酔いがひどい、入浴で気分が悪くなったり気を失ったりする、嫌なことを考えると気分が悪くなるなどの症状もあります。
起立性調節障害の原因は?
起立性調節障害の原因は、自律神経のバランスが崩れること。本来は立ち上がると自律神経が働いて血圧や心拍数が上がり、脳に血液が送られます。しかし、自律神経のバランスが崩れていると、脳に十分な血液が送られなくなってしまいます。
自律神経とは交感神経と副交感神経で構成されており、交感神経は動物が敵と対峙して戦うときの戦闘モードです。心拍数は上がり、血圧をあげてくれます。副交感神経はおやすみモードです。血圧を下げて、心拍数もゆっくりになります。この交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまうのが、起立性調節障害となります。
また、さまざまなストレスや不安が起立性調節障害の症状を悪化させます。起立性調節障害の症状により日常の活動量が低下すると、筋力が低下し、自律神経のバランスがさらに崩れてしまうことに。そうなると、下半身への必要以上に血液が移動して、 脳への血流が減り、さらに活動量が低下するという悪循環に陥り、さらに症状は悪化します。
また、脱水によって症状が悪化することもあり、夏場には熱中症にかかりやすくなります。
起立性調節障害の診断方法
病院での診断は、立ちくらみ、朝起きられない、気持ち悪い、だるい、気を失う、頭痛など、基本的には先にお伝えしたような症状があること。そして、同じような症状を起こす体の病気ではないことを確認します。
心電図や立位負荷試験(15分くらい立った状態で血圧と脈拍、心電図を計り続ける)という検査をすることもありますが、あくまでも補助的な診断といえるでしょう。
起立性調節障害の治療は?
まずはじめに、本人と保護者、場合によっては学校の先生に対して、起立性調節障害の理解をしてもらうことが大事です。
「起立性調節障害は体の病気であり、気合いや根性、気持ちの持ちようだけでは治らない」ということです。その上で、薬による治療や生活指導、ストレスや不安を減らすための環境調整を行います。
薬物療法
血圧を上げる薬や睡眠のリズムを整える薬を使うことがあります。また、漢方薬が有効なことがあります。いずれにしても、薬だけで良くなることはほぼありません。生活指導や環境調整も同時に行います。
生活指導
立ちくらみに対しては、座った状態や寝ている状態から起き上がるときには、頭を急に持ち上げずに、頭を下げた状態からゆっくりと持ち上げて起き上がるようにします。
また、起立性調節障害は、脱水によって症状が悪化することも。脱水予防のために、経口補水液などを用いて、水分と塩分をしっかりと摂るようにしましょう。

体を動かすことが、自律神経のバランスを整えるにはとても良いのですが、起立性障害の子の多くは、0か100かどちらかという、0―100思想を持っている傾向があります。
つまり、「朝起きて、だるいから今日は1日寝ている」というような感じで、昼くらいから徐々に体調がよくなってきても、1日中横になってベッドの上で過ごしている子も少なくありません。
「朝、頭痛くて学校にいけない。遅刻するくらいなら、1日休んでしまおう。」というような感じの子も多くいます。
私の外来では子供たちに、「無理をする必要はないけど、動けるようになったら、動ける範囲で動いてごらん。学校に行けなかったら行かなくてもいいけど、玄関から少し外に出て散歩してごらん。散歩も無理だったら、ベランダで太陽の光を浴びるだけでもいいよ。できることから始めて、できること、できる範囲をだんだんと増やしていってごらん。」と説明しています。
また、睡眠リズムを整えることも大切です。眠れないからと遅くまでテレビやビデオを見たり、ゲームやスマホを見ていたりすると、余計に眠れなくなります。長時間のスクリーンタイム(パソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を見て過ごす時間)は、身体活動が減少し、体力低下や姿勢を悪くするなどの問題が起こります。
身体活動が減ると疲れないから眠くならないので、余計に夜に眠れない原因にもなります。さらに姿勢が悪くなると、子供でも肩こりが起こり、それが頭痛の原因になり、これが身体活動を減らす原因にもなり、ますます悪循環から抜け出せなくなります。
私の外来では「スクリーンタイムは、寝る2時間前まで。寝る前の2時間は寝る準備をしましょう」と説明しています。
環境調整
子供の心理的ストレスや不安を軽減することは、とても大切です。保護者、学校関係者が起立性調節障害について十分に理解して、無理に学校に行かせるのではなく、子供たちができることをサポートしてあげながら、できることを徐々に増やしてあげることが大切です。
最後に
子供が希望すれば、スクールカウンセラーや児童精神科などを受けることも治療選択としてあります。心理カウンセリングなども有効な方法の一つといえるでしょう。
発達障害や発達に凸凹がある子たちが、社会の中での生きづらさを感じていることもあるので、子供の特性を親が知って、適切な声掛けやサポートの方法を学ぶことも大切です。
文:十河剛