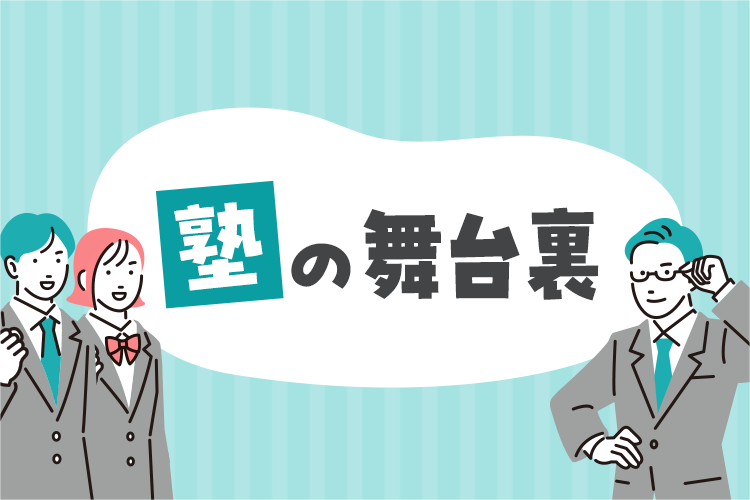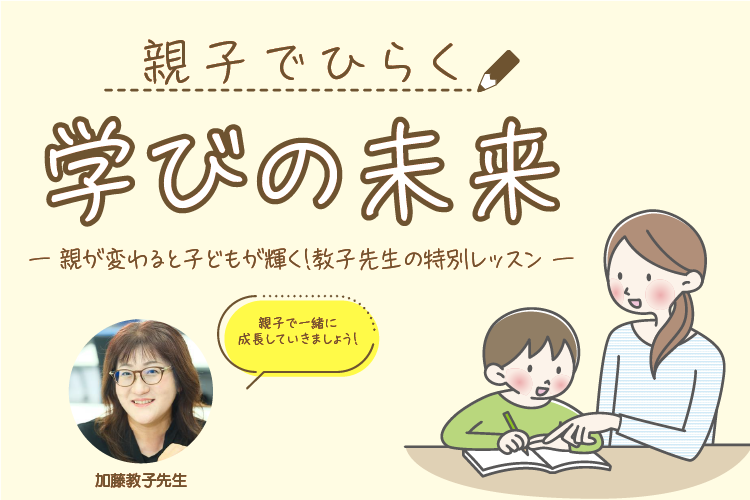「塾の舞台裏」では、個別指導塾で多くの小中高生を指導している講師にインタビューしています。今回は、生徒を見てきた中で感じる「モノの見方」について話を聞きました。

塾講師 金川俊也(かながわ・としや)
大学卒業後、会社員や事業の立ち上げなどを経験したのち独立。愛知県大府市に「個別指導塾アドバンス」を設立し、勉強のやり方と合わせて、未来を生きるためのヒントを子どもたちに伝えている。自身も小3と中2の2児の父として子育てに奮闘中。
視野が狭いと、解けない問題

中学3年生の国語の教科書に登場する「故郷」という中国の小説があります。作者である魯迅(ろじん)が生きた時代は1881~1936年。時代の違い、都会と田舎、身分の差、貧富の差など……、それによる心の変化が描写された作品ですが、そもそもこれらの「違い」が分からないと、読みづらい内容です。小説は、時代背景や情景描写が分かると理解が深くなりますが、それらが想像できないと「意味が分からない」となりかねません。
理解を深めるためには、さまざまなジャンルの本を読むことをおすすめしたいのですが、読書は日々の積み重ね。すぐに結果は出ないですし、読書が苦手な子もいますよね。例えば、歴史を扱った漫画を読むことでも時代背景を理解する助けになりますし、映画やドラマを見るでもOK。他にも、いろいろな場所に出かける、人に会うなど、好きな方法でいいので、歴史や異文化に触れて視野を広げる行動をとってみてください。
YouTubeやTikTokなどのSNSは、よく視聴するジャンルの動画が自動的に表示されるので、見聞きする情報が偏ってしまいがちです。
広い視野を養い、さまざまな立場の人の気持ちを理解できるようになることは、国語の文章理解の対策としてだけでなく、これから社会に出た時にも間違いなく役に立つはずです。
大人も価値観のバージョンアップを

子どもが成長する中で、さまざまな価値観に触れて視野を広げることは大切ですが、大人にとっても同様と言えるかもしれません。
親世代である昭和・平成の「常識」が、令和の時代では「非常識」となっていることが多々あります。例えば、性差別的な言動や、「給食は残さず最後まで食べなければいけない」というルールも変わってきましたよね。コミュニケーション手段もオンライン化が進んでいます。
どちらが良い・悪いではなく、時代は変わっています。自分の価値観を変えていかないと、今を生きる子どもたちに、時代に合わないことを押し付けてしまいかねません。
私自身も子どもと接したり、授業を担当してくれている大学生と話したりしていると、違いを実感し、「自分自身も変えていかなければ」と思わされることがよくあります。
もうすぐゴールデンウイーク。大人も子どもも、さまざまなものを見て、聞いて、経験して、自分自身をバージョンアップできるといいですね。