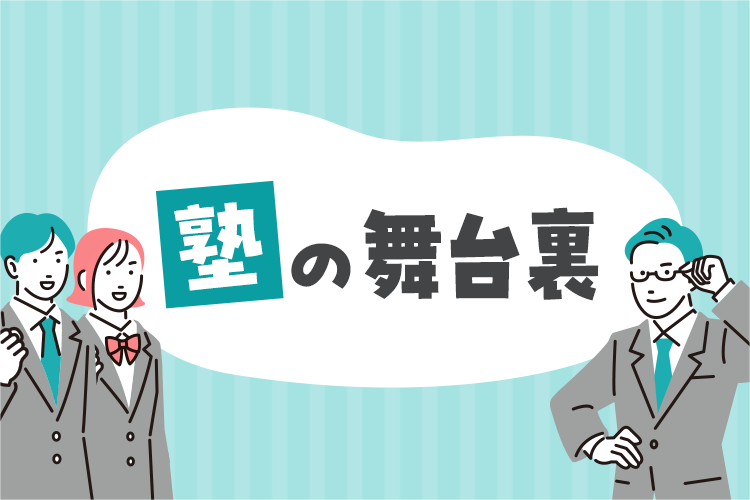- 投稿日
公共の場でのマナーやお友達とのコミュニケーションなど、子育て中の親御さんであれば、お子さんの「しつけ」について、あれこれ考え、試行錯誤しているのではないでしょうか。
「しつけ」は漢字で「躾」と書きます。この漢字は日本特有のもので、中国には存在しないとか。身を美しく保つことの大切さを込めた、日本らしい漢字ですよね。今回は、子どもの自立を促す「しつけ」についてお伝えしていきます。

一般社団法人シヅクリ 代表 山下由修(やました・よしのぶ)
静岡市内の小・中学校で勤務した後、市立清水江尻小学校の校長として、県内初のコミュニティースクールを創設、運営。また、市立大里中学校の校長を務めながら、フレックスタイム制の導入や校内フリースクールの開設、プロジェクト型の校内組織運営などに着手 。2019年、一般社団法人シヅクリを創設し、静岡を拠点に、人材育成に取り組んでいる。
「しつけ」の本来の意味は?

「しつけ」とは礼儀作法や、やってはいけないことを教えるという意味です。
「しつけ」は、元来着物を縫う時に、仮に縫っておく「しつけ糸」からきているという説があります。着物が縫い上がると、しつけ糸は外されます。つまり、「しつけ」は「外す」ことが前。いずれは親元から巣立っていく子どもにとって、「外す」というのはとても重要な意味を持ちます。
ひょっとして、私たちは「しつけ」の名を借りた、ただの「おしつけ(押しつけ)」をしていないでしょうか。
「しつけ」から考えるヒント
人は感情的になった時、次のようなの3つの行動をとると言われています。
- 戦う
- 逃げる
- 我慢して従う
戦うことを選ぶと、周りから人が離れていくかもしれません。逃げると、一時的な衝突は避けられますが、自分の気持ちはスッキリしません。我慢して従うと、心のエネルギーの低下を招いてしまいます。
時には子どもに対し、感情的になることもあるでしょう。そのような時、どのようにしたら、子どもの自立を育む「しつけ」に結に付けられるでしょうか。
そんな時は、親自身がまず、自分自身を見つめ直してください。そして、相手に伝えたいメッセージは何かを考え、それを届けるよう意識してください。
「しつけ」は日々の積み重ねで、根気も体力も必要です。子どもの「しつけ」を通して、子どもの見本となれるよう、親御さん自身もわが身を鍛えていってください。
そして、ありったけの愛情とメッセージを添えて、子どもに語りかけてください。子どもの自立と未来のために。
文:⼭下由修