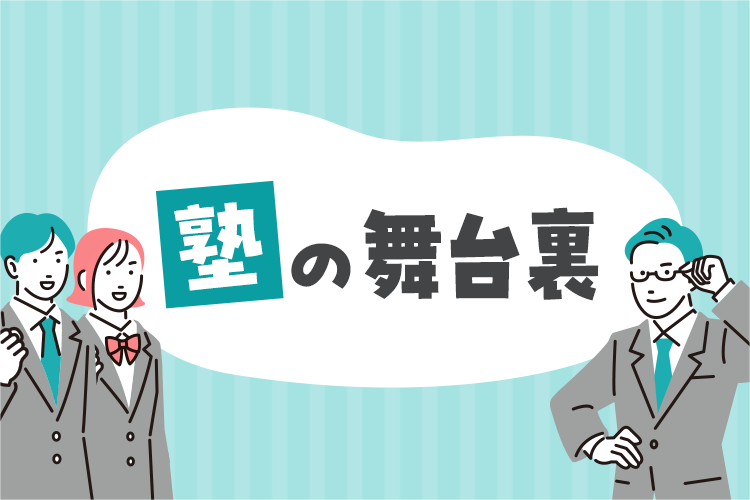小学校高学年で学ぶ内容は、それまでと比較し、より「考える」ということに比重が置かれています。それぞれの教科の知識から、深く考えて先を見通し、周りとコミュニケーションをとることで、「生きる力」の養成を目指しています。
この生きる力の軸は「道徳感」です。 そして、この軸をつくってあげられるのは、最も身近にいる親御さんではないでしょうか。今回は、小学校高学年からの学びの変化と、考える力の育み方をお伝えします。

塾講師 渡邉智治(わたなべ・ともはる)
愛知県一宮市にて「進学塾 翔和」を経営。塾講師歴は25年以上。犬山市教育委員も務めている。
具体的→抽象的な問題に
小学校高学年になると、学校で学ぶ内容が「具体的な問題」から「抽象的な問題」に変わっていきます。一例として、算数の文章問題を紹介します。
A.小学4年生の問題
【問題】720このビーズを 9 人に同じ数ずつ配ると、1 人分は何こになりますか?
B.小学5年生の問題
【問題】1㎏ のねだんが 980 円のハムがあります。
①このハムを 4.5㎏ 買うと、 代金はいくらになりますか?
②このハムを 0.8㎏ 買うと、代金はいくらになりますか?
Aの問題では、「割り算を使って計算する」という判断がすぐに出来ると思います。Bの問題では、大きさや重さを想像しにくいため、学校や塾では、絵や図を描いて具体的にイメージしてから、式を作り、解答するよう指導しています。
小学5年生以降の算数で出題される文章題は、このような「抽象的な問題」になり、頭の中でイメージするのが難しくなります。
これは、算数だけではありません。社会ではデータを読み取って自分の考えをまとめたり、理科の実験では結果を予測し、さらにその結果をもとに考察したり、すべての教科で「考える力」が試されるようになります。
考える力を育む「道徳感」とは?
抽象的な問題を解くのに、考える力が求められるのと同じように、道徳感を育むためにも、考える力が求められます。逆に考えると、日頃から道徳感を育てることが、子どもの考える力を育むことにもつながると言えます。
道徳感を育てるといっても、難しいことはありません。具体的には、次のような社会生活を送る上では当たり前のことばかりです。

・悪いことをしたら謝る
・ルールや約束、時間を守る
・忘れ物をしない
でも、「この当たり前が、意外と出来ない……」ということも多いでのはないでしょうか。
子どもの道徳感を育てるには?
普段の生活の中で、交通ルールや乗り物に乗る際のマナー、公園で遊ぶ時の遊具の順番待ちなどで、お子さんにルールを教えたり、アドバイスしたりすることはありますよね。
その際、「〇〇の時はどうしたらいいかな?」「どうして△△しなければいけないのかな?」など、お子さんに 「考える種」を与えてください。そして、しっかりと意見を交わし、会話のキャッチボールをし、コミュニケーションとってください。
子どもは子どもなりの考え方や視点を持っています。大人が考える「正解」とは異なっていても、頭ごなしに否定してはいけません。まずは、きちんと考えられたことを褒めて、認めてあげてください。なぜなら、そうやって誠実に考えようとする姿勢や態度こそが、豊かな心と自立心を育むからです。
親としては国語、算数、理科、社会、英語の学習をつい優先しがちです。近い将来にある受験のことを考えると「学校のテストで高い点数がとれる」ことは、ひとつの安心材料になるのではないでしょう。
でも、どうか学習面以外でも、お子さんの様子をよく見て、お子さんの話をよく聞いてください。親御さんのそうした行動こそが、お子さんの考える力を育むことになるのだと思います。
文:渡邉智治