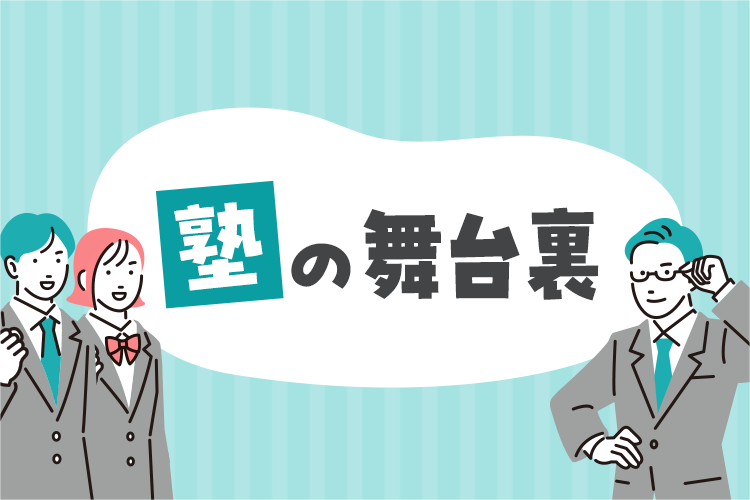- 投稿日
寒い日が続く中、吹きっさらしの木の枝にアゲハ蝶のさなぎを見つけました。越冬し、春のふ化を待っているのです。アゲハ蝶の成長は子どもの成長に重なります。小学生は幼虫、中学生はさなぎの年代とも言えるでしょうか。
今回は、さなぎの成長になぞらえて、子どもの成長と親としての役割についてお伝えします。

一般社団法人シヅクリ 代表 山下由修(やました・よしのぶ)
静岡市内の小・中学校で勤務した後、市立清水江尻小学校の校長として、県内初のコミュニティースクールを創設、運営。また、市立大里中学校の校長を務めながら、フレックスタイム制の導入や校内フリースクールの開設、プロジェクト型の校内組織運営などに着手 。2019年、一般社団法人シヅクリを創設し、静岡を拠点に、人材育成に取り組んでいる。
アゲハの成長と子どもの成長

アゲハ蝶の幼虫は、成長とともに脱皮を重ね、緑色から鮮やかな黄緑色の終齢幼虫(ふ化する直前の幼虫)に成長します。人間でいうなら小学校入学、ピカピカの1年生が進級を繰り返し、たくましい小学6年生へと成長する姿に重なります。
昆虫の成虫、つまりアゲハ蝶の大きさは、終齢幼虫時の大きさです。つまり、3㎝の幼虫は、3㎝以上の成虫にはなれません。
人間でいうなら小学校時代に多くの栄養を摂取できたかどうかが、人としての器の大きさに影響するということでしょうか。
中学校に入学すると、幼虫がさなぎに変身するように、子どもたちは全く違った形に姿を変えます。さなぎは、留まった環境の色に染まります。緑色の葉の上では緑色に。茶色の枝の上では茶色に。そして、無理に触ると奇形してしまうことも。
つまり、中学校時代は、自己を確立する時期であり、同年代の仲間関係が大きな影響力を持ちます。集団のありようを視野に入れたデリケートな関わりが必要です。
子どもの成長=教えること?
幼虫、小学校時代は、基礎・基本を身につけるとともに、人としての核をつくる大切な時期。そして、多くの親御さんが「わが子にはたくましく・しなやかに育って欲しい」と願っているのではないでしょうか。
しかし、その結果を求めるあまり、私たち大人は「子どもの成長」=「教えること」と思い込んでしまっている傾向があります。
でも、考えてみてください。生まれた子どもは世界中どこでも2、3歳になると母国語を話し始めます。親が子どもに言葉を教えなくても、子どもが分かっても分からなくても、毎日語り続けることで、ある日子どもは言葉を話し始めるのです。つまり、「教える」ではなく、「伝わる」ということです。
京都にある燈園学園の相大二郎学園長は、次のように言っています。
人は、「教わる」教育によって知識や技能を身につけ、人は、「伝わる」教育によって人間性や価値観、生活習慣などを身につけます。
これを言い換えると、人間性や価値観、生活習慣はどんなに教えてもらっても身につかないということ。つまり「親の背中を見て子は育つ」ということです。
こちらが意識していない日常のしぐさや癖を、わが子から見い出したことはないでしょうか。まさに、これが「伝わる」です。
誰に対しても明るい挨拶をする家族のいる環境で育った子どもは、自然と明るい挨拶をするように。また、電車の中でお年寄りに席を譲っている親の隣にいる子どもは、自身も自然と席を譲るようになるはずです。
子どもを取り巻く大人達の率先垂範(そっせんすいはん、人の先頭に立って物事を行い、模範を示すという意味)こそが、幼虫、小学校時代の子どもにとって、極上の栄養になるのではないでしょうか。
家庭でも、私たち大人が少しだけ「伝わる」を意識し、行動すること。それによって、子どもの将来、人としての器の大きさを育むことにつながると考えています。
文:⼭下由修