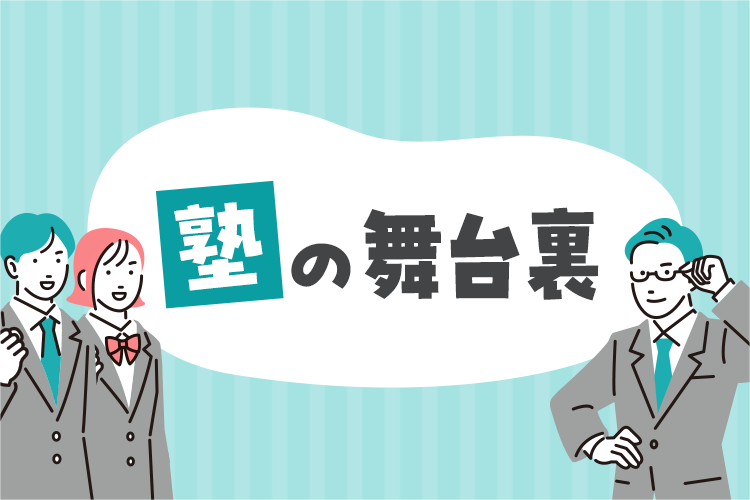- 投稿日
70年前から、校則なし、制服なし、自由自治を大切にし、驚異的な進学率を誇る中学校があります。体育祭も合唱祭も、実施する・しないまでも自分たちで決断し、全てゼロから生徒たちがつくり上げ、遂行している学校です。
この中学校の生徒と教師の関係性について、その秘訣を「呼び方」と「呼ばれ方」からひも解いてみました。

一般社団法人シヅクリ 代表 山下由修(やました・よしのぶ)
静岡市内の小・中学校で勤務した後、市立清水江尻小学校の校長として、県内初のコミュニティースクールを創設、運営。また、市立大里中学校の校長を務めながら、フレックスタイム制の導入や校内フリースクールの開設、プロジェクト型の校内組織運営などに着手 。2019年、一般社団法人シヅクリを創設し、静岡を拠点に、人材育成に取り組んでいる。
先生を「ちゃん」付けで呼ぶ学校

驚異的な進学率を誇る中学校があります。その学校では、生徒たちが担任の教師を「ちゃん」付けで呼んでいました。
その学校で、探究プログラムのオリエンテーションを行ったことがあります。その時、私は生徒に問いかけてみました。
「明治、大正は『強さ』を求めた時代。そして、昭和、平成は『豊かさ』を求めた時代です。では、令和は何を求める時代だと思いますか?」
真っ先に手を挙げた生徒は、「人間力」だと回答。次に指名した生徒は、「楽しさ」だと答えました。
その理由を聞くと、「感じること、みんなで考えること、楽しむことはAIには出来ない。だからこそ、それを大事にすべきだと思います」と答えてくれました。
何としなやかで、柔らかく、洞察力にあふれる発想でしょう。きっとこの子たちなら、自らの力で未来をつかみ取り、地球規模の課題でさえ、さらりと解決していくのかもしれないと思いました。
その後、教師たちとの雑談していると、「この子たちほど、生意気で、賢く、行動力に満ちた生徒はいない」と、みなが微笑みを浮かべながら話していました。
そこに1人の生徒が通りかかりました。
教師「わかった。昼休みでいいかな?」
生徒「お願いします。また来ます」
「Kちゃん」「Gちゃん」というのは、担任の教師の名前です。あまりにも自然な会話にスルーしそうになりながらも、この呼び方に「?」マークが浮かびました。
教師に聞いてみると、入学当初はもちろん「先生」と呼ばれていたそうです。しばらくして呼び捨てで呼ばれる時期があり、そして今は、「Kちゃん」「Gちゃん」と呼ばれているということでした。
自分の「呼ばれ方」は?
私も、自分が何て呼ばれているか、振り返ってみました。親には終始一貫、呼び捨てで呼ばれています。
幼いころは友達に「よっちゃん」と呼ばれていました。小学校に入ってからは、男子には「山ちゃん」、女子には「よしのぶさん」と呼ばれるようになりました。
中学校では「山下くん」、高校・大学では「だいすけ」とあだ名で呼ばれていました。教員になってからは、定番の「山下先生」、管理職時代は役職名で呼ばれることが多くなりました。
「ちゃん」「さん」「くん」「あだ名」「先生」「役職名」、それぞれの呼ばれ方に思い出が蘇ります。その時々の感動や落胆、喜び、悲しみ、楽しさ、切なさが周りの人々の面影とともに映し出されます。
自分の「呼び方」は?
親のことは、「お父さん」「お母さん」と呼んでいました。大学生になった頃くらいから「おやじ」「おふくろ」に変わりました。
友達の呼び方は、呼ばれ方と同様に変化していきました。
教職時代は、子どもたちのことを授業など、公の場では「さん」「くん」と敬称をつけていましたが、個々に対しては名前を呼び捨てで呼んでいました。
妻と息子、娘に対しては名前を呼び捨てで呼んでいます。
それぞれの呼び方は、関係性や場の違いによって、込める思いも変化していっていることが分かります。
呼び・呼ばれて何を受け取る?
欧米ではファーストネームで呼び合うことは当たり前のことであり、部下が上司を名前で呼ぶことも珍しくないようです。
日本では「名前で呼び合うこと」へのハードルが高く、家族や友人など、近しい間柄以外で、名前で呼び合うことはごく稀です。
そういう意味でも、「名前で呼び合う」ことをお互いが認めるのは、当事者同士の関係性がそれだけ深まっているという証だとも言えるのです。つまり、呼び方は相手との距離をそのまま示しているといっても過言ではありません。親密度を測る上で、非常に重要な要素だということになります。
確かに、仲が深まってくるとフランクに呼び合い、本音と本音が交わされるようになります。そして、建設的な対話が生じてきます。実はこの関係性と親密度こそ、何かを生み出す原動力になっていくのです。
私は長い教員人生の中で、子どもたちに「山ちゃん」と呼ばれたことはありません。一定の距離感を保ったままだったのかもしれません。
先生から、呼び捨てに、そして「ちゃん」付けという子どもたちの呼び方の変化は、信頼と親密度の変化そのものです。「Kちゃん」「Gちゃん」と呼ばれている教師に対して、きっと子どもたちは、「平等な関係で何でも言い合え、相談できる人」として全幅の信頼を置いているのでしょう。
相田みつをさんの書を思い出しました。
「その人の前に出ると絶対にうそが言えない。そういう人を持つといい」
何でも話せる安心感が、子どもたちのエネルギーに火を点け、わくわくする明日をつくっていくことでしょう。
文:山下由修