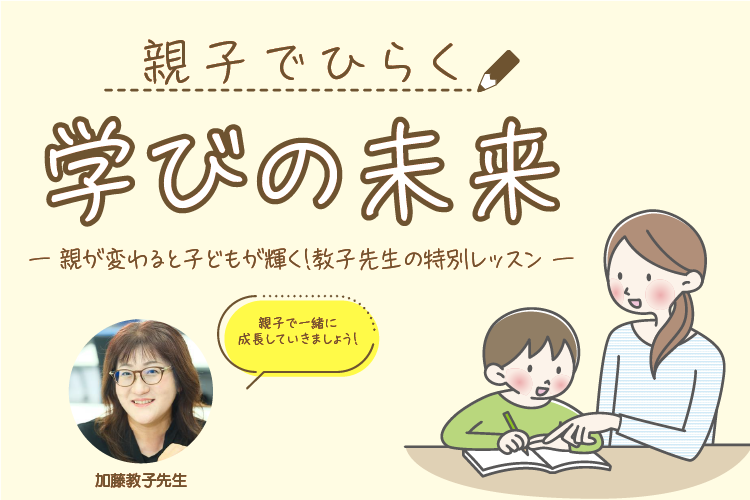「小1プロブレム」「中1ギャップ」「高1クライシス」などの言葉を聞いたことはないでしょうか? これらの言葉は、子どもが進学する時、さまざまな壁にぶつかることを指していています。今回は、以前から重要な教育課題として捉えられてきた進学時の問題と対策についてお伝えしていきます。

塾講師 渡邉智治(わたなべ・ともはる)
愛知県一宮市にて「進学塾 翔和」を経営。塾講師歴は25年以上。犬山市教育委員も務めている。
進学時に問題が起きる原因は?
「小1プロブレム」は、小学校に入学したばかりの子どもが、新しい環境になじめず、集団行動がうまく出来なかったり、授業を静かに受けられなかったりする状態が続くことです。
幼稚園や保育園で、子どもたちは遊びを通じた教育によって主体性を育んできました。ところが、小学校に入ると突然、規律を重視した教育を受ける。つまり、先生の言う通りに行動することを求められるようになります。これによって戸惑ってしまうのが原因の1つと言われています。
「中1ギャップ」は、中学校に入学したばかりの生徒が、環境の変化や学習内容の変化になじめない現象です。具体的には「集団が大きくなり、人間関係が複雑になる」「1番上の学年から、急に1番下の学年になる」「定期試験の結果が重視されるようになり、負荷が増える」など、さまざまな変化がその要因だと言われています。
「高1クライシス」も、高校へ入学したばかりの生徒が学習や生活面での変化に適応できない現象です。学区が広範囲になることで、幼少期からのつながりが切れて新しい人間関係を構築しなければならないこと。学力レベルの近い同級生に囲まれることで、自分の得意分野がそれほどでもないと気づき、自信を喪失することなどが主な原因だと言われています。
「円滑な接続」が、ポイントに

ここで大切なのは、子どもの発達や学びの「連続性を確保すること」です。
進学時の不適応の問題がメディアなどで取り上げられるようになったのは比較的最近のことです。しかし、学校現場では20年近く前から校種間(幼稚園・保育園と小学校、小学校と中学校、中学校と高校)の連携や接続の在り方に大きな課題があると指摘されていました。
現在では、異なる校種についての理解を深め、乗り入れ指導や出前授業、授業交流、運動会や合唱祭の見学など、さまざまな形での連携や接続が進められています。
学習指導要領では、「初等中等教育の一貫した学びを充実させるため」として、異校種間の円滑な接続が重視されています。「プロブレム」「ギャップ」「クライシス」を解消するための一貫教育や、子どもの発達の段階を考慮した異校種間の連携は、今後もますます進んでいくと思われます。
学びの連続性を確保するには「一貫教育」を実施していくことが理想です。小学校なら、今学んでいることが中学での学習にどう繋がっていくのかを伝え、中学校では小学校における学習の内容、程度を把握した上で授業を行う。さらに、中学校においても、今学んでいることが高校での学習にどう繋がっていくかを伝え、学習の連続性を確保することが大切です。
しかし、実際の学校現場でこれを行うのはなかなか難しい状況なのではないでしょうか。
子どもに対して大人ができること
多くの塾では、これから「中学準備講座」、「高校準備講座」が開催されます。これらの講座は、今まで学んだことを復習し、さらに入学してから学ぶ内容を先取りして学習します。こうした講座を活用することで、学習面だけでも心に「自信」と「余裕」をもっておくこともおすすめです。
春休みは何となく、そしてあっという間に過ぎていきます。塾に限らず、家庭でも「復習 8割、先取り2割」で、学習習慣の確保に注力してください。また、親御さんは新しい環境に不安を抱えるお子さんに寄り添い、密にコミュニケーションをとっていくことも大切です。
子どもたちは、少しずつ成長して「今」があります。いろいろと言いたくもなりますし、何かと反抗的な態度をとる子もいるかもしれません。人生の先輩として見守りながら、新生活に挑む子どもたちを、温かく応援してあげましょう。
文:渡邉智治