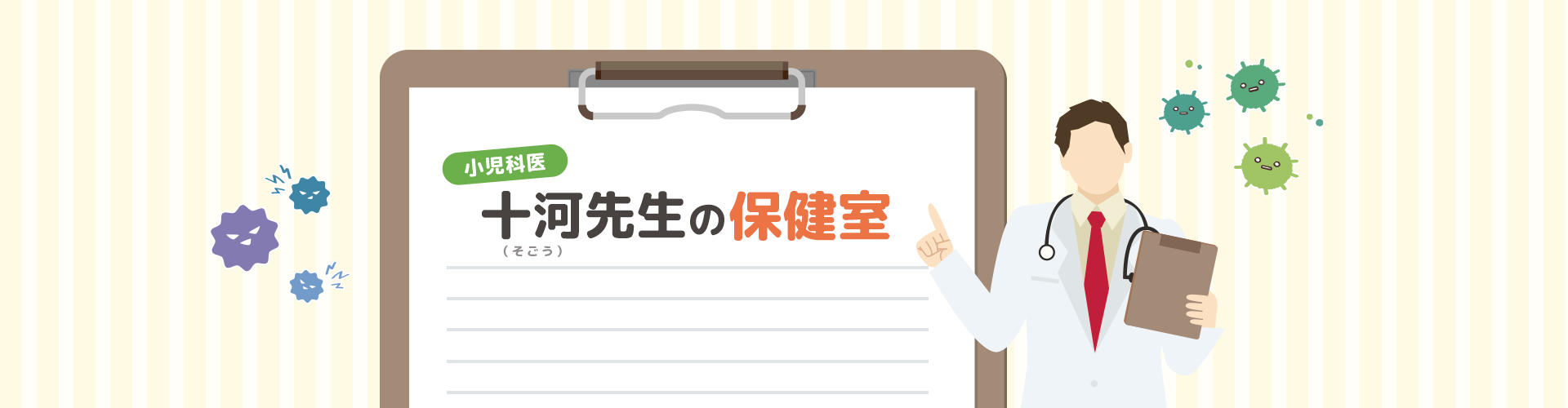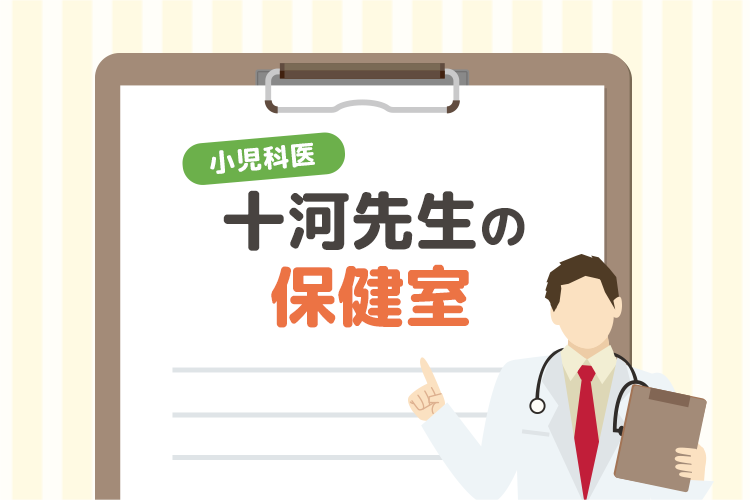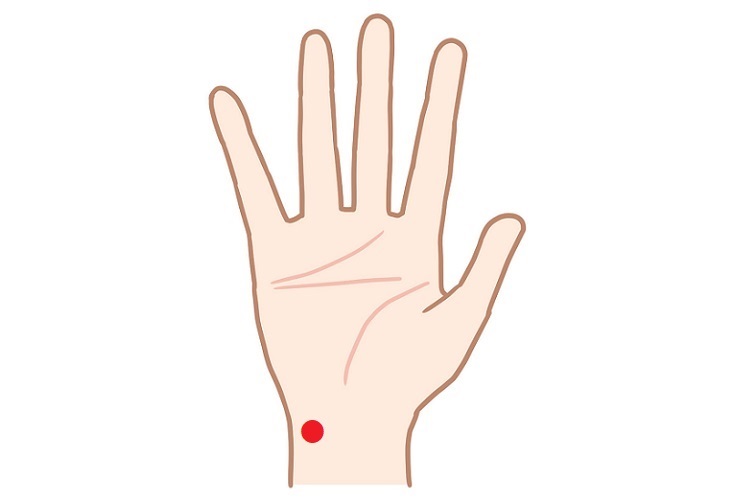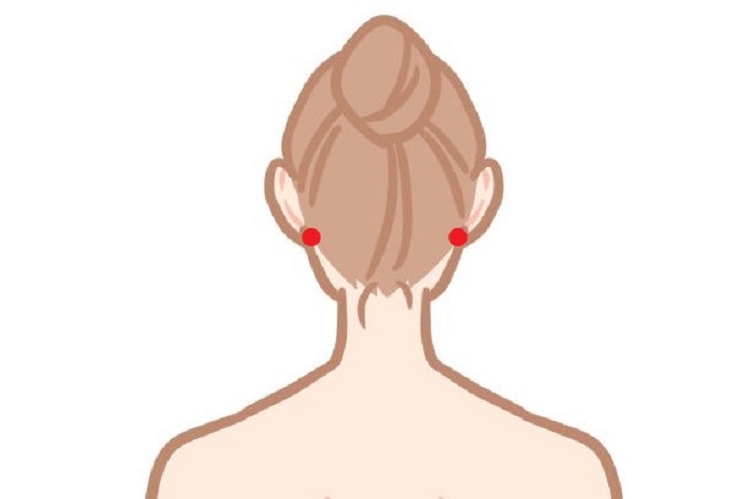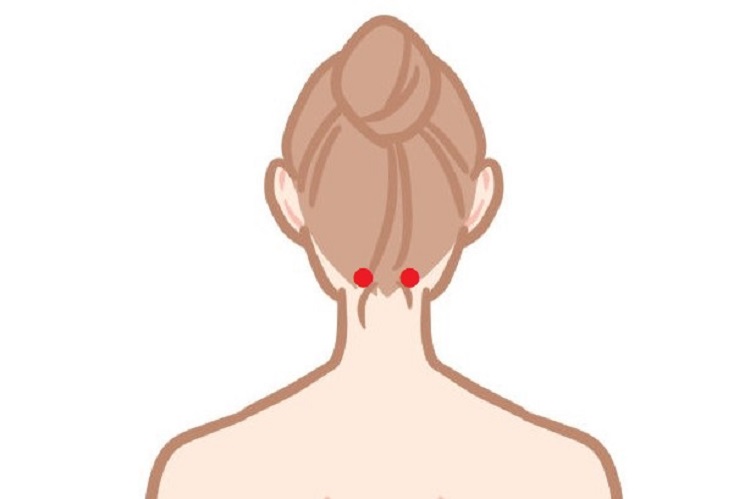「学校保健調査報告書」(文部科学省)によると、肥満度20%以上の子供たちが、昭和40~50年頃と比較して約2倍に増えています。
昭和の小学生を描いたアニメ「ちびまる子ちゃん」のまるちゃんのクラスは26人。太っているのは小杉くん1人でした。当時の肥満の子の割合が5~7%程度なので、現実とそれほどかけ離れていないと思われます。
現在の肥満の子の割合は、およそ十数%なので、クラスにもう1人か2人くらいいる計算です。今回は、大人と子供の肥満の診断方法、子供の肥満の原因、脂肪肝についてご紹介します。
大人の肥満の診断方法は?
大人の場合、肥満の診断方法として、BMI(Body Mass Index)という指標を用います。
自分の体重(kg)を身長(m)の2乗で割ったものがBMI値です。
①身長をmに換算し、2乗する
1.58(m)×1.58=2.4964
②体重を①の答えで割る
55(kg)÷2.4964≒22.03=BMI値
日本肥満学会では、BMI値が25以上だと肥満、22を適正体重(標準体重)としています。同じ肥満と言っても、欧米ではBMI値が30を超える人が多く、日本は25以上30未満の人が多いです。
子供の肥満の診断方法は?

子供の場合、成長により身長と体重のバランスが変わります。そのため、子供の肥満を診断するのに、日本ではBMIより肥満度を用います。肥満度は標準体重に対して、実測体重が何%上回っているかを示すもので、以下の式で計算されます。
肥満度(%)=(実測体重-標準体重)÷標準体重×100
標準体重は、性別、年齢、身長別に設定されています。
幼児の場合、肥満度が15%以上を「太り気味」、20%以上を「やや太り過ぎ」、30%以上を「太り過ぎ」とし、児童では、肥満度が20%以上を「軽度肥満」、30%以上を「中等度肥満」、50%以上を「高度肥満」としています。
より簡易的に判定する方法として、日本小児内分泌学会が公表している肥満度判定曲線を用いることも多いです。良かったら参考にしてみてください。
子供の肥満の原因は?
肥満の子供の増加と反比例するように、子供たちの運動能力が低下しています。
1964年の東京五輪以降、内容の見直しや変更はあるものの、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」が実施されてきました。この調査によると、1985年頃をピークに、その後の約10年間、急激な運動能力の低下が見られます。
ちなみに家庭用ゲーム機が普及するきっかけとなった、任天堂の「ファミリーコンピューター®」の発売が1983年。今の携帯型ゲーム機の原型とも言える「ゲームボーイ®」の発売が1989年です。これは、子供たちの体力低下の時期と見事に一致しています。
子供たち運動量の指標として1日あたりの歩数を見てみると、1980年代の小学生男子の歩数は2万歩を超えるのに対し、2013年の調査では約1万2000歩と半分近く減っています。
体力・運動能力の低下にはいろいろな原因が考えられますが、家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機、スマートフォンの普及の影響もあるのではないでしょうか。社会や環境の変化に伴い、運動不足に陥りがちな状況を念頭に置き、日常的に体を動かす時間を増やしていきたいですね。
脂肪肝とは?
脂肪肝とは、肝臓に脂肪が溜まる病気です。大人の場合、飲酒が関連していることも多く「アルコール性脂肪肝」と、お酒以外の原因による「非アルコール性脂肪肝」に区別されます。非アルコール性脂肪肝の場合、肥満(太っていること)が関連していると考えられます。
当然ですが、子供ではお酒による脂肪肝はほぼゼロであり、基本的には非アルコール性脂肪肝です。子供の非アルコール性脂肪肝の原因も大人と同じように肥満がほとんどです。太っていないのに脂肪肝が疑われる場合は、生まれつきの病気が隠れていることがあるので、詳しい検査が必要となります。
肥満と脂肪肝を放置すると?
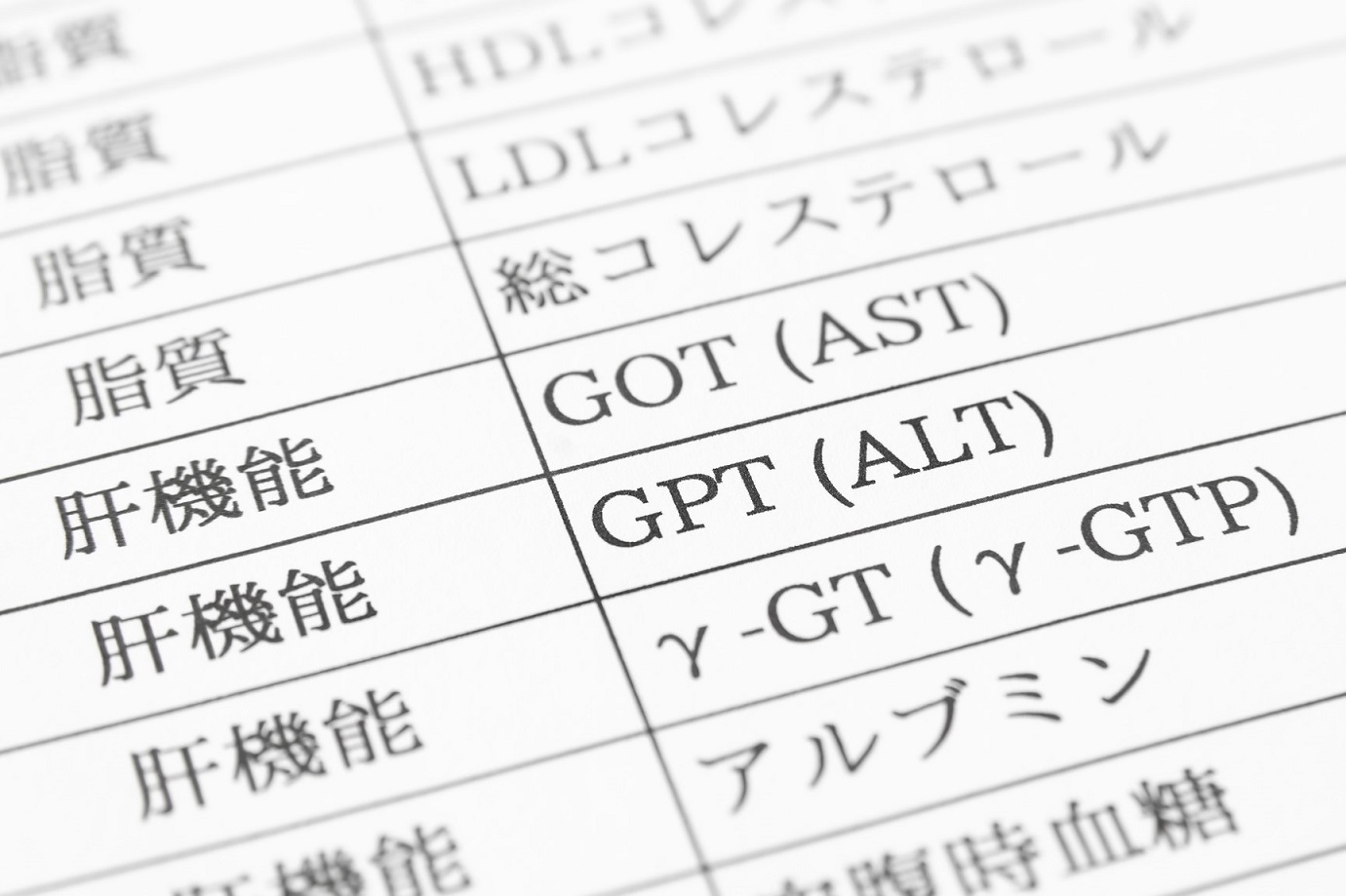
以前、無料で子どもの脂肪肝検診を行ったところ、参加者の約半数が脂肪肝でした。もちろん、脂肪肝検診を受けに来るのは肥満の子ばかりなので、肥満の子の約半数が脂肪肝だと言っていいでしょう。
これまで脂肪肝は「体重を減らせば治る」とされ、それほど深刻に考えられていませんでした。しかし、非アルコール性脂肪肝の子でも、肝臓に炎症が起こって脂肪肝炎になり、肝硬変を引き起こすことが分かってきました。
さらに、小児でもメタボリックシンドロームを起こすこともあります。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積に加えて、「脂質異常(高脂血症)」「高血糖」「高血圧」のいずれか2つ以上が該当した状態を言います。心筋梗塞や脳卒中の予備軍とも言える、注意すべき状態です。
非アルコール性脂肪肝の子を20年間追跡した研究によると、一般の小児人口グループと比較して、明らかに生存率が低いことが報告されています。つまり、脂肪肝がある子の方が長生きできないということです。
脂肪肝にならないためには?
脂肪肝にならない、または脂肪肝を治すためには、年齢相当のバランスの良い食事と適度な運動の2つに尽きます。
乳児期の肥満の多くは、成長とともに自然に改善し、特に治療の必要はありません。しかし、1歳を過ぎてからの幼児期の肥満は、小学生以降、さらに成人になっても改善することなく、続いてしまうことが多いです。
また、幼児期の前半に2回以上肥満を指摘された場合、12歳時点でも肥満であるリスクが通常と比較して5倍高くなることも報告されています。
そうならないよう、適度な運動を意識しましょう。日本では、「子どもの身体活動ガイドライン」(日本スポーツ協会)や「幼児期運動指針」(文部科学省)などで、毎日合計 60 分以上、体を動かすことを推奨しています。世界保健機関(WHO)や、多くの国々でも、毎日合計 60分以上の身体活動が推奨されています。
幼児期に体を動かして遊ばないと、本来獲得されるべき運動能力が身に付かず、「運動が苦手な子」になってしまいます。苦手なものは楽しくないので、余計に運動しなくなるという悪循環にも陥ってしまうかもしれません。
太っている子の親もまた、太っていることが多いです。子供だけに運動させたり、食事を制限したりしても効果はありません。もし、親のBMI値が25以上であれば、親子で一緒に食習慣と運動習慣を見直すことをおすすめします。
文:十河剛

十河剛 (そごう・つよし)
済生会横浜市東部病院小児肝臟消化器科部長。小児科専門医・指導医、肝臓専門医・指導医、消化器内視鏡専門医・指導医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。
診療を続けていく中で、“コーチング”と“神経言語プログラミング(NLP)”と出会い、2020年3月米国 NLP&コーチング研究所認定NLP上級プロフェッショナルコーチの資格を取得、2022年全米NLP協会公認NLPトレーナーとなる。また、幼少時より武道の修行を続けており、現在は躰道七段教士、合気道二段、剣道二段であり、子供達や学生に指導を行っている。
「子供の一番星を輝かせる父親実践塾」Voicyにて毎朝6時から放送中。
動画セミナー『子供の天才性をハグくむ叱らなくても子供が勝手に動く究極の親子コミュニケーション術』