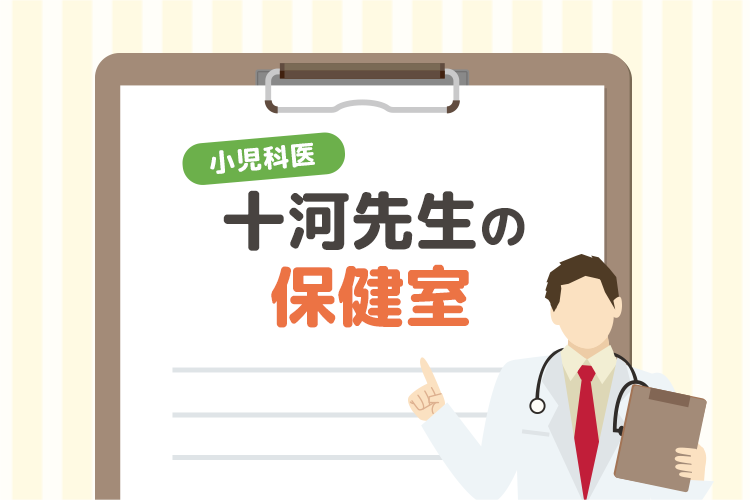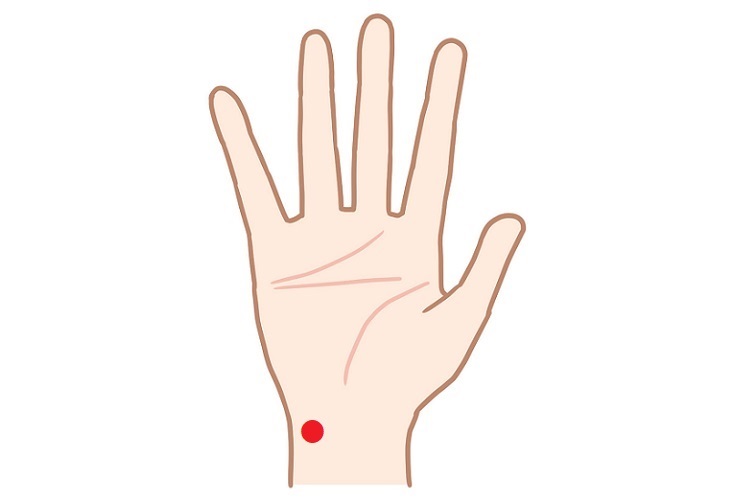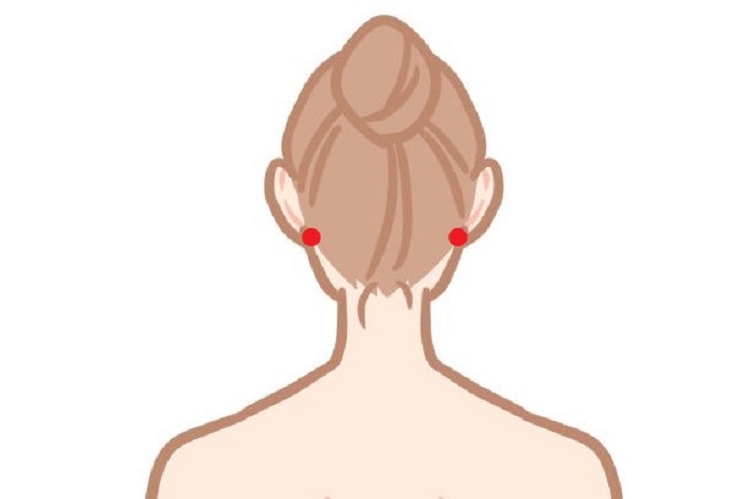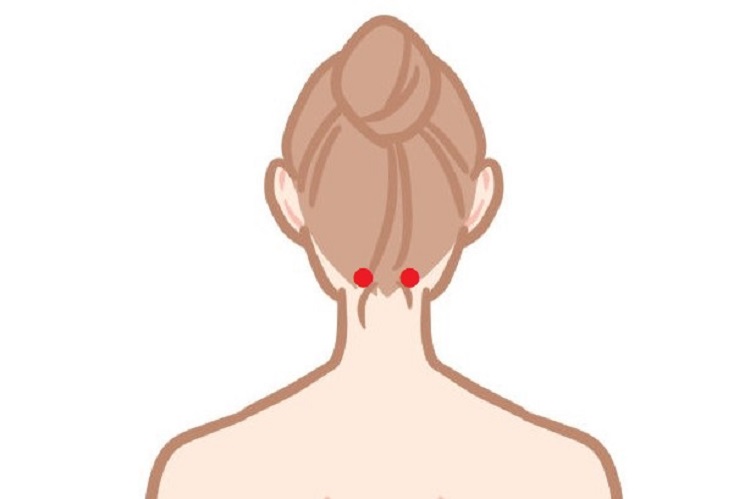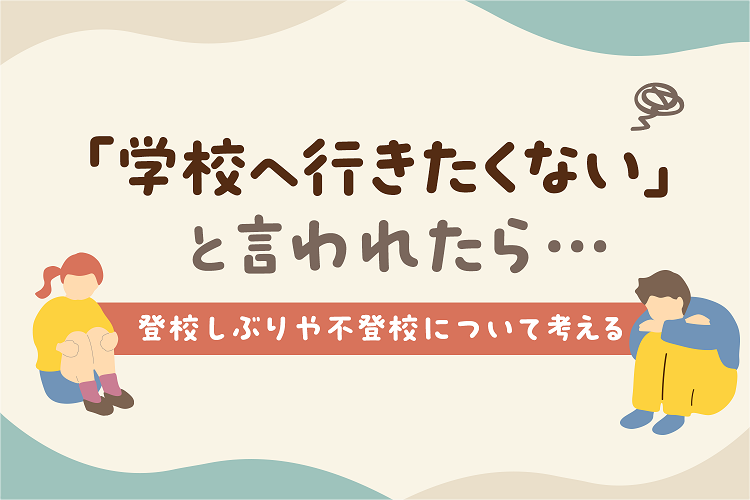成長期の子どもにとって、食事や睡眠などの規則正しい生活習慣は学力や体力面にも大きく影響します。特に食事面など生活習慣の乱れは、体力面だけでなく学習意欲の低下などの一因が指摘されています。
「最近子どもの集中力の低下が気になる」
「子ども向けの食事メニューが知りたい」
「成長期の子どもにしっかり食べさせたい」
子どもの集中力や学力を高めるための食事メニューや食生活のコツを食育インストラクターで自身が運営する学童で手作りおやつを提供する中村さんに解説いただきました。
授業に集中するには朝ごはんを

子どもの発達や成長には個人差があるものの、カラダの発達やこれからの生活リズムを作る大事な時期です。子どもの生活リズム向上を図るため、文部科学省は「早寝早起き朝ごはん」を提唱しています。(※1)
文部科学省の調査によると、朝ごはんを毎日食べる習慣のある子どもは、朝ごはんを食べていない子に比べて学力調査の得点が高い傾向にあるそうです。
朝ごはんを抜いてしまうと、エネルギー不足により、授業に集中できなかったりイライラしたり、キレやすかったり、子どもの気持ちも安定しません。
大人は朝食を抜いてもお腹が空いたら何か口にすることができますが、学校生活を過ごす子どもたちはそうはいきませんよね。
成長期の子どもにとって、大人と同じ感覚で朝食を抜くことは避けたいものです。
規則正しい生活リズムを整えることは健康面だけでなく、子どもの集中力アップにも繋がります。まずは朝ごはんをしっかり摂ることから始めてみましょう。
手軽に作れる平日の朝ごはんは?

では、朝ごはんにはどのようなものを食べればよいでしょうか。
以下に摂りたい栄養をご紹介します。
朝ごはんに摂りたい栄養
① ブドウ糖:ご飯やパン、イモ類など
脳に十分なエネルギーが供給されないと、カラダを動かす力はもちろん、集中力も散漫になりがちです。脳のエネルギー源であるブドウ糖は、朝にしっかり摂っておきましょう。(※2)
ブドウ糖はご飯やパンなどの穀物類やいも類、果物などに多く含まれています。
糖質などのエネルギー源が不足すると疲れやすくなったり集中力が低下したりすることがあります。とくに午前中は授業が長く続くので、エネルギー源となるごはんやパンなどをしっかり摂ることをおススメします。
② カルシウム:チーズや大豆、海藻類など
炭水化物だけをとるのではなく、カルシウムをプラスするよう心掛けていきましょう。
カルシウムには、強い骨を作る以外にも精神を安定させる作用もあると言われており、意識的に摂りたい栄養素です。(※3)
乳製品や大豆製品、ひじきなどの海藻類、切干大根などの乾物に多く含まれています。また、カルシウムの吸収をサポートしてくれるビタミンDなども合わせて摂るようにしましょう。
パンであれば、チーズトーストにするだけでカルシウムも摂れますよ。
手軽な朝食メニュー
- 梅干し入りおにぎり
ごはん(糖質)+海苔(カルシウム)+梅干し(クエン酸) - チーズおかかおにぎり
ごはん(糖質)+チーズ(カルシウム)+鰹節(ビタミンD) - しらすチーズトースト
パン(糖質)+チーズ(カルシウム)+しらす(カルシウム、ビタミンD)
市販のものをうまく活用したり、曜日によって朝食パターンを決めたりして、時間がない朝でも充分な栄養を摂れるよう工夫していきましょう。
集中力につながる食生活

カラダを作る大事な時期、子どもの食事の内容にも気を配ってあげたいですよね。
ただ、特別なことは必要なく、目指すは「バランスの良い食生活」です。
普段の食生活で気を付けたい3つのポイントをまとめました。
- おやつやジュースはほどほどに
- よく噛んで食べる習慣づけを
- 加工食品の使いすぎに注意
おやつやジュースはほどほどに
子どもにとっておやつは大切なエネルギー源です。
糖分が不足すると、脳を動かすためのエネルギーが不足し集中力が低下してしまいます。
一方で、高カロリーなものや甘いお菓子の摂りすぎは、集中力の低下を招くこともあります。
お菓子や糖分の多いジュースの摂りすぎはさけましょう。
10歳前後の子どもに必要な一日のエネルギー量は1800kcal~1950 kcalです。(※4)
おやつのカロリーの目安はこの1割程度、できれば200 kcal以内です。
量が多い市販のスナック菓子は、予め食品保存用袋などで小分けにしたり小皿に分けて出したりすれば摂りすぎを防げますよ。
よく噛んで食べる習慣づけを
健康のためにも、よく噛んで食べるようにと言われたことはありませんか?よく噛むことで脳が活性化し、集中力の向上やストレスの緩和に繋がると言われています。
根菜やきのこなど食物繊維の多い食材を使用したり、野菜を少し大きめに切ってみたりすると、噛む回数を増やせます。おやつにナッツやドライフルーツなどを取り入れるのも良いでしょう。
加工食品の使いすぎに注意
便利な加工食品ですが、塩分や添加物の摂りすぎは控えましょう。
塩分や添加物の摂りすぎは、単にカラダの成長だけでなく、精神や感情への影響も懸念されています。日々の食事づくりの中で添加物を減らせるよう意識できるといいですね。
最後に
育ち盛りの子どもにとって食生活の乱れは、体力面だけでなく学習意欲の低下、集中力低下の一因とも指摘されています。
さまざまな健康法が推奨される中で、糖質制限や朝食抜きが取り上げられることもありますが、成長期の子どもには避けるようにしましょう。
子どもの学力を食事からサポートできるよう、生活リズムを整え、手軽に栄養価をプラスしてわが家流の工夫をしていけるといいですね。
文:中村美帆

大手金融機関にてファイナンシャルプランナーを経験。
食育インストラクター、食生活アドバイザー、ジュニアアスリートフードマイスター。
子育て支援団体「ガレット」を立上げ、親子おやつ教室やイベント企画、子ども食堂を主宰。
2021年より、子どもと地域の未来を見据え、合同会社BASE ONを設立。
2023年4月より学童保育施設「かざみどりKids」を開設。
三児の母。三重県伊勢市出身。
参考
※1 できることからはじめてみよう早ね早おき朝ごはん│文部科学省
※2 朝ごはんを食べないと?│農林水産省
※3 大切な栄養素カルシウム│農林水産省
※4 食事摂取基準|厚生労働省