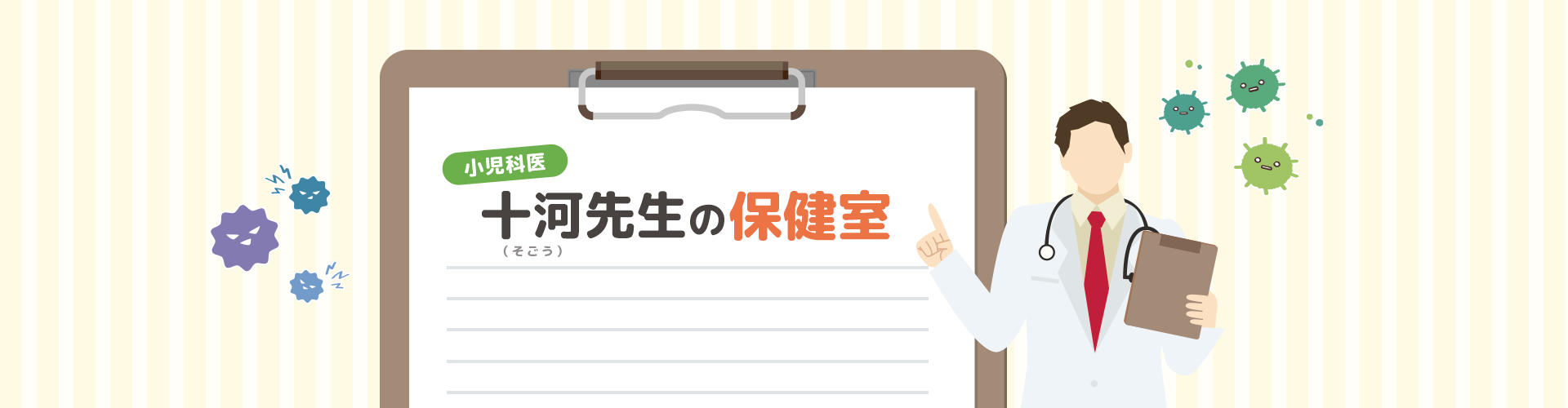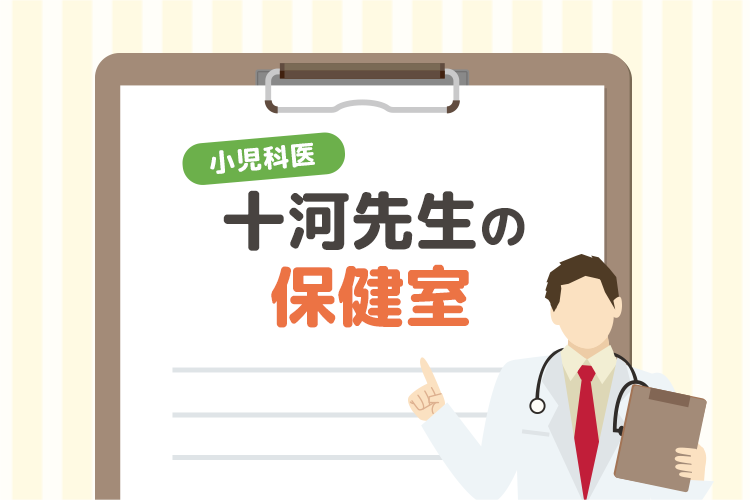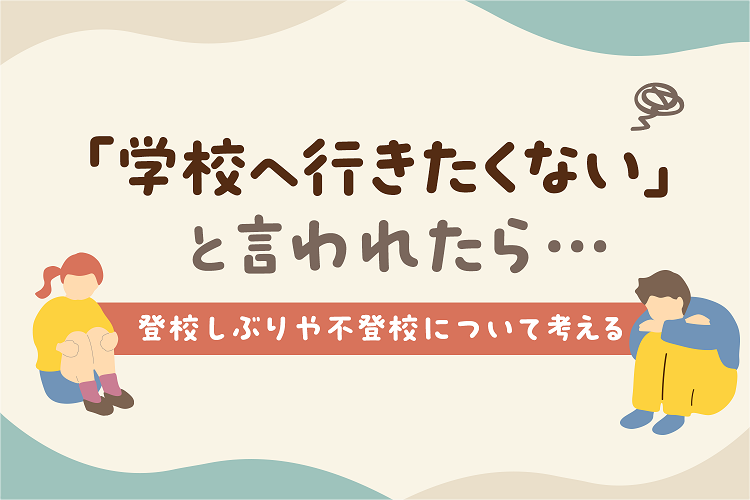「お腹の冷え」による症状は、冬場より夏場に多い傾向にあります。残暑が続く季節、暑い時期にこそ気を付けたい子供のお腹の冷えについて、原因と対処法を紹介します。
夏にお腹が冷えるのはなぜ?
連日、熱中症のニュースが流れるような暑い時期ほど、「お腹の冷え」による症状で受診する子供が多くいます。詳しく話を聞いてみると、「よくアイスを食べる」「冷たい飲み物を頻繁に飲む」など、胃腸を冷やす原因となるような食生活をしていることが多いです。
冷房や学校でのプールの授業など、体を冷やすことになる要因が、夏場に多いことも関係しているでしょう。症状が強いと、汗だくになるような気温であるにも関わらず、ジャージの上にウィンドブレーカーを着て来院する子もいます。夏場に腹巻をしていたり、肌着のお腹の部分にカイロを貼っていたりする子もいます。
「お腹の冷え」による症状は?
お腹の冷えによる症状は、下痢や腹痛が多いですが、中には便秘になる子もいます。ただし、便秘の場合は食欲低下や嘔気、胃痛、腹部膨満などの症状が伴っている傾向があります。
外見的な特徴としては、やせ型で顔色が悪く、姿勢も良くない傾向があります。大半は女の子ですが、男の子もいます。手足を触ると冷たいことも多いです。年長児だと肩こりや頭痛、倦怠感を訴えることもあります。
腹巻とお腹の症状の関係は?

10年以上前の話ですが、他の病院の小児科で研修中の医師(大学卒業後4年目)から、「臨床研究の相談に乗ってほしい」と言われました。臨床研究をしようと思ったきっかけは、便秘の子を診療している時に腹巻をしている子が多いのに気付いたことなのだとか。その医師は、「腹巻は下痢をする子がするものだと思っていたけれども、便秘にも効果があるの?」と疑問を持ち、私に連絡をくれました。
彼は、小児科外来に来た0~15歳の544人の保護者にアンケート調査を行い、①排便習慣 ②食事内容 ③便秘の既往 ④腹巻きの有無と着用頻度などを調査しました。その中で、「週7回以上排便がある」と答えた子の腹巻の使用状況は以下の通りです。
巻いていない 58%
この研究は、便秘の子に対して腹巻を着用させ、排便回数が増えるかを試したものではありません。単に下痢の子が腹巻を巻いているだけという可能性もあります。しかし、この結果から、腹巻を着用することが便秘の改善に一定の効果があるのではないかと彼は結論付けました。
最近は少し減った印象がありますが、以前は、私の外来に来る子の中で、腹巻をしている子も多かったです。子供のお腹の病気を専門とする私の立場から見ても、お腹が冷えることでさまざまな症状を引き起こし、また、腹巻をすると、その症状が一定程度改善することは確かだと思います。
西洋医学では「冷え」について、それほど重要視されておらず、あまり医学部の授業で教わることもありません。そのため、冷えによる症状がみられる子には東洋医学の漢方薬と生活指導で対応しています。
「冷え」の考え方は?
東洋医学においては、胃で吸収された食べ物は、消化吸収を担う臓器「脾(ひ)」に送られ、体を温めたり、エネルギーになったりする「気」をつくるものだと考えられています。
さらに、胃と脾は密接につながっていると考えられており、脾でつくられる「気」が足りなくなると、消化機能に異常をきたすとされています。逆に、冷たいものをとりすぎると胃の機能が低下し、脾の機能も落ちてしまいます。このように胃と脾は相互に作用しているのです。
気とは「元気」「やる気」「勇気」などの気です。気が足りなくなると、元気がなくなり、行動を起こすやる気もなくなり、困難なことに立ち向かう勇気もなくなってきます。不登校や学校の行き渋りにも関連すると考えられます。
西洋医学にはない考え方ですが、冷えを考える時にはとても大事な思考だと思います。
「お腹の冷え」の対策は?

お腹の冷えの対策として、まずすべきなのは、胃腸を冷やす原因となる冷たい飲み物や食べ物を避けること。消化に良い温かいものを食べるようにしましょう。エアコンの温度も高めに設定し、場合によっては腹巻やお腹にカイロを貼ることもすすめています。
学校のプールで体が冷え、体調を崩してしまうのなら、必要に応じて見学することも1つです。スイミングスクールに通っている場合には、休会や退会を考えても良いかもしれません。
私の外来では、冷えの症状に対して漢方薬を処方することが多いですが、漢方薬の独特な味やにおいが苦手な場合は、お湯で溶かして、砂糖とショウガのしぼり汁を入れることで、飲みやすくなります。
ショウガには体を温める効果があるため、漢方がどうしても飲めない子には、ショウガ湯をすすめることもあります。無理のない範囲で、体を動かすことも大切ですが、脾でつくられる「気」がない状態ですので、無理をし過ぎて、疲れないように注意しましょう。
今回は西洋医学の考え方ではなく、東洋医学や漢方の考え方です。医学書に載っているものではなく、私の経験を優先していることをご理解ください。
西洋の薬ではなかなか良くならない症状は、お腹の冷えが原因のことがあります。気になる場合は、漢方に詳しい小児科医に相談してみても良いかもしれません。
文:十河剛

筆者:十河剛 (そごうつよし)
済生会横浜市東部病院小児肝臟消化器科部長。小児科専門医・指導医、肝臓専門医・指導医、消化器内視鏡専門医・指導医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。
診療を続けていく中で、“コーチング”と“神経言語プログラミング(NLP)”と出会い、2020年3月米国 NLP&コーチング研究所認定NLP上級プロフェッショナルコーチの資格を取得、2022年全米NLP協会公認NLPトレーナーとなる。また、幼少時より武道の修行を続けており、現在は躰道七段教士、合気道二段、剣道二段であり、子供達や学生に指導を行っている。
「子供の一番星を輝かせる父親実践塾」Voicyにて毎朝6時から放送中。
動画セミナー『子供の天才性をハグくむ叱らなくても子供が勝手に動く究極の親子コミュニケーション術』